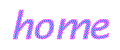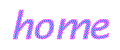�\�@�Ǘ��l�̂Ԃ₫�@�\
| ������@�w�����َE�l�����x�@���I�@�����Y |
�������A�����������ɉ����āA�A�a�ɂ܂镶�́B����Ȃ�̗\���m�����K�v�ŁA���Ȃ��Ƃ��w�t�@�E�X�g�x�i�Q�[�e��j���炢�͓ǂ�ł��������B����̊����ɁA�����������̐��E�ɂ̂߂荞��ł䂭�C�z�B������͓ǂ݉����Ɍq����A�����ւ̓��̂�ł�����B�������ɂ͂Ȃ�Ƃ��Ă��ǔj���������̂��B�����Ƃ��A��x�ǂ����Łu�ǔj�v�ƌ����邩�ǂ����c�B�쒆�ɓo�ꂷ�铙�g��̎����l�`�A�e���[�Y�̕s�C�����ɁA�R�~�b�N�́w���炭��T�[�J�X�x���v���o�����B�����w����A�B���p����ŁA���҂ƌ˘f���ɐg�k��������X�ł���B |
| 2006.4.15 |


�w�p���`�m�`�x�@��c�@���Y
�Ȏq��{�����߂ɒE�˂��A�V��g�Łu�l�a��ш�v�Ƃ��������ꂽ�j�́A��Ƃ̐��U��`���B
���̒j�A�g���ш�Y�ɂƂ��Ă̋`�Ƃ́A�˂ւ̒��߂ł��Ȃ��A�܂��Ă⑸�c���̎u�ł��Ȃ��A�Ȏq���Q������~���A�������炦�����邱�Ƃł������B�܂��A���̏����̍\�����ʔ����B�����̐����ؐl�����̘b�ƁA�g�����g�̂ЂƂ���̏�ʂ����݂ɑ}�����A����ɋg���Ƃ����l���̗֊s������ɂ��Ă䂭�Ƃ����d�|���B��K�z�A�o�҂��Q�l�ƕ݂̂Ȃ���A���̂�����̐l�X�͔ނ��Ă��A�������ɂ͂����Ȃ��B�Ȃ�قǁA�V�����Ƃ�J���킯�ł��Ȃ��A����Ȃ������ۂ��Ȏu�i���荂���n�ƑG�̎u�j�̎�����ł͂��邪�A�ނ͂��̖��̒ʂ�A���Ɏu���Ȃ��邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł���B���ɔ����ڂ͂Ȃ����A�����ċ��œ����ʂƂ����A�ꌩ��������j�̌��p�ɁA���m�����z���ČǍ��̐Ȃ������ށB�암�����̔�������i�A�����a��̉��������A���̕���Ɉ�w��Ɩ��킢��Y���āA���S�[���B
�V��g�̐����c���A�g���̊W�҂ɘb���ĉ���Ă���l���B����͂����炭�A�q���V����z�肵�Ă���̂ł��낤�B�k�C���o�g�A�ҏW�ҁA�吳���A�V��g�O����c�Ƃ������Ƃ��ƍ�����ƁA����ȊO�ɍl�����Ȃ��B
����͗]�k�����A�{��ł̉��c���i�́A�i�n�łł̂���₩�Ȉ�ۂ͔����A��Ȃ���Ȃ����鈫���Ƃ��ĕ`����Ă���B���A����͂���Ŗ��͂������Ĉ����Ȃ��B
�ȉ��A��ۂɎc��ӏ������B
���˂������Ȃ���A�������͍˂����������䂦�ɐ��̒��̎d�g�ɉ����ׂ���A�R���ׂ����Ȃ����̗���ɉ����������B�g���ш�Y�͂������������̐��`��������B�i�ē���k�j
���R�����Ⴀ�������ɁA���ɕ��͋����Ă���邪�ˁB���������Ă̂��������Ⴍ��܂���B�{���͂������̂ق��������Ɗ̐S�ȂB��������m��˂��j�ɁA���ɕ��Ȃ킩������B�i�����k�j

�w���̏��x�@�����@���[
�����̏W�Ɉُ�Ȃ܂ł̚n�D���݂��鋳�t�A�m�؏����B�ނ͒N�ɂ��s������������V�픭���̗��ɏo�����A�Ƃ���C�ӂ̏W���ɒH�蒅���B���ɖ����ꂽ�ƂɌ�������l�X�A�����́A�����l�ԂE���ɂ��Ď����A���Ԓn���̂悤�ȏ��ł������B�j�͂��̂����̈ꌬ�Ɋċւ���A���~���̘J����������邱�ƂɂȂ�B���x���E�o�����݂Ă͎��s���A�������A�s�ɂ܂�Ȃ�������������l���B�������A�o�܂Ȃ��J��Ԃ��ɂ���ē���Ɖ����B����Ă��܂��A�s�𗝂��S�n�ǂ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������Ƃ��B���Ƀs�����h���A���̍�����܂ł��肶��ƘM��ł����j���A�����ē����悤�ȉ^����H��p���h�N�X�͐▭�ƌ��������Ȃ��B
���肦�Ȃ���ʐݒ�B�V���[�����A���X���ɌX�|�������[�Ȃ�ł͂̓��قȐ��E�ɁAჂ��悤�ȓ������o�����B�ז��ȕ`�ʂƔ�g�̑��p�́A�����܂ł��Ȃ�ǂ݂Â炢�B���A�����ɂ��ʂ��郌�g���b�N�̍I�݂��͓��M�ɉ�����B�ȉ��ɂ��̈��������悤�B
���������A���߂��݂̂�����ŁA�j���B���̔j�Ђ��A�ӎ��̕\�ʂɂ�����āA�ԂԂ̔��_�ɂȂ����B
���X�R�b�v����ɂ����Ƃ���ɁA�܂肽���ݎ��̎O�r�̂悤�ɁA��J�ō������邸��ƒZ���Ȃ�B
���ꖇ�ꖇ�A���̔�����ނ��Ă͗����Â���A���̃i�C�t�B
�����ɂ��炵���n�̂悤�ɁA��ǂ�J���A�ւɂȂ�A���炰�ɂȂ�A�����ʂɂȂ�A���q�j�͌^�}�ɂȂ��āA�ɂ���ł����B

�w�Ԃ����x�@�����@���[
�l�̋��b�I�Z�ҁB���Y��`�̉e�����F�Z���A�O�ꂵ�����z���E���A��߂�ꂽ���������Ԃ�o���B
���Ԃ���
���ȏ��ɂ��̗p���ꂽ���ƂŁA���[�̍�i�Q�ł͂����Ƃ��L���ł���B�u����̉Ƃ��ꌬ���Ȃ��͉̂��̂��낤�H�v�Ƃ����₢�ɁA�Ƃ�ł��Ȃ��������o���A�t�]�̔��z�����j�[�N�B���������ꂽ�l�Ԃɑ��āA���Ԃ̊�Ƃ����炪�A�₽���ǂɂȂ�B�e���o���ꂽ�j�͑����Ƃ���ق�A�₪�āA�قꂽ���ɕ�܂��A�������̑��݂ƂȂ��Ă��܂��B���̂ƈ��������ɁA�u���̉Ɓv����ɓ��ꂽ�j�́A�ق̐Ԃ��������Ȃ���A�Ȃ����f�r��������B
���^�@��
������A�J���҂̉t�����ۂ����X������B��ӂ���A�㗬�K���ւƂ���͍L����A�Ō�����ςȃm�A�܂œۂݍ��܂�A���̍^���ɂ���Đl�ނ͐�ł���B�w�Ԃ����x�ł͂ق�A�w�^���x�ł͂Ƃ낯��l�ԁB�l�̂̂U�O���͐����Ƃ�������A�u�t�̐l�ԁv�̂��Ƃ��b���A���ɐ^������ттĂ���B�㏸�u���œo��߂�A����Љ�ւ̌x�����B���R�̂Ă�����߂����̂͂����A�����A����Ƃ����ύt������A����������~�߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�����@�̃`���[�N
�n�R�ȊG�`���̘b�B���@�̃`���[�N�ŁA�ǂɃp����R�[�q�[��`���ƁA����s�v�c�c�B�q�ǂ��̍��A����Ƃ悭������z���������̂ł���B�������A���������E�����E�K���ŏI���Ȃ��̂����[��i�ł����āA����ȗ\���ʂ�̌������҂��Ă���B�g�̒��A�ǂƃ`���[�N�̐����ł����ς��ɂȂ�A���ɕǂƓ������Ă��܂��A���S���N�B���炴��Ƒ͐ς��Ă䂭�NJ��́A�w���̏��x��f�i�Ƃ�����B
�����@��
����l�̗ʎY���肪�����\�[�Z�[�W�H��ŁA���ɐl���\�[�Z�[�W�̉��H���J�n���ꂽ�B�n���K�͂Ől�������ƐH�ƕs�����i�s����Ƃ����ݒ�B���オ������ۑ�Ɠ�d�ʂ��ɂȂ��āA�u���b�N�W���[�N�Ə�������Ƃ��ł��Ȃ��B�O���e�X�N�ȕ`�ʂ̎c���́A�f����茾�t�̕����n���ɂ����Ȃ��悤���A�ǂ��ɂ��㖡�������B

�w���@�j�x�@�����@���[
�l�ԎЉ�́u���邱�Ƃƌ����邱�Ɓv�̕s�@���ȊW�ɂ���Đ��藧���Ă���B���������j�́A�u����ꂸ�Ɍ��邱�Ɓv��]�ށA�ɂ߂Ď��ȃ`���[�ȑ��݁B�͂����茾���Ă��܂��A����߂�ꂸ�ɔ`��������Ƃ����A�N������ߎ��~�]�̐��s�҂Ȃ̂ł���B
���̕���̓��ِ��́A�܂�Ŗ��̐��E�̂悤�Ɉ�ѐ����Ȃ��Ƃ��낾�낤�B�܂����ɁA��҂��܂߂ĉ��l���̔��j���o�ꂷ��Ƃ������ƁB�u�ڂ��v�͌��J�����}�������m�ꂸ�A��Â���������R�ォ������Ȃ������B���ꂾ���ł͂Ȃ����ɂ���ẮA�u���Ƃ���A�v�ł���\��������A�`����������ꂽ���ND�Ƃ��l�����A��l���̎����ɔ��肽���Ă��A�l�i���ۂ�֊s�ɂ܂�Ŗ������Ȃ��B����́A���͋C�����͐��X�����c���Ă���̂ɁA�l���̊炪�ǂ����Ă��v���o���Ȃ��A�����̂��̂̈�ۂɋɎ����Ă��Ȃ����낤���B�������A�u�ڂ��v�Ɗ䔠�j�̉�b�̒��ŁA���̂悤�Ȃ��Ƃ܂łۂ��ƌ��ɂ���̂��B�u�������������A���������g�A�ڂ��̋�z�̎Y���ɉ߂��Ȃ����Ƃ���������F�߂Ă��܂����ɂȂ���v�A���̈ꕶ���ǂ��������̂��낤�B�u�������v�Ƃ͊䔠�j�ƊŌ�w�̂��Ƃ��w���̂����A�z�ʒʂ�ɑ�����Ȃ�A��ҁA�܂苟�q���������Ă���C�������u�ڂ��v�̈ꕔ�ł���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
�����Ď��ɏグ���邱�Ƃ́A���Ԃ̊ϔO���������蔲���Ă���Ƃ������Ƃł���B�C�ӂɊ��������́A���C���܂�ʼn����Ԃ������Ǝ��葱���A���̒��̗����́A�ǂ�Ȃɏ����Ă������Ղ�]�����c����Ă���B�o���ɒH�蒅�������̈�����A�����ɓ�����ɓ��ݓ����Ă���Ƃ��������z�B�ǎ҂̓��r�E�X�̖��H�ɁA������R�Ɨ����s���������Ȃ��B
����Ȃ����ǎ҂̂��߂ɁA���[���^���Ă��ꂽ�q���g�B�L�k���̋��b�����A���̏����𗝉������ŏd�v�Ȏ肪����ƌ����邾�낤�B�u�L�k���̓�����k���ƁA���ɂȂ�����������v�Ƃ����B���̌`�������S���߂̒��ɉ������܂ꂽ�䋛�́A�₪�ēM�ꎀ��ł��܂��̂����A�u������o�߂�O�Ɏ���ł��܂����̂ŁA��������ȏ�o�߂�킯�ɂ͂����v���A�䋛�͖����i���A���̒��ɕ����߂��Ă��܂��c�B�܂肱�̏������A���Ɏ���ł���j�́A������o�߂Ȃ��܂܂ɒԂ�����L�Ƒ�����Ȃ�A���ׂẴs�[�X���[�܂�Ƃ���ɔ[�܂����p�Y���悤�ɁA�[���ł���̂ł���B

�w���@��x�@�����@���[
�\�@���̕�e�ł��������ӂƂ��ꖂ�A�R���N���[�g�̕ǂ�����ݏo�������H���r�߁A�����N�������߂��Ȃ��Ȃ������̈�l�����̖���ɂ����݂��@�\�@�������߂����錋���ɁA���̕���̈ٗl�����\�o���Ă���B��̉����g�����n�l�ԁA�Ԃ�Ԃ�̐��S���̂悤�ȗn���ǂ̏����A�Ȑ����a�̂��̕�i�A�J�`���ƌ��ɐ��܂�����F�̂ӂƂ�j�c���������Ȃ�悤�Ȋ�����Ȑ������������A�[�w�ɐ��ވ������Ȑl�Ԃ̑f��Əd�Ȃ荇���B
���H�����Ȃ�{���j���A���H�̂悤�ȑ�a�@�̊��v�ɂ͂܂�A�����Љ����ł���Ƃ����A���[���ӂ̋t�]���ہB��r�I����̍�i�ł���{���́A�ϐg�A���ŁA�ǂƂ����ނ̃��`�[�t�̏W�听�ƌ����邾�낤�B�����^��Y�����킭�A�u�ނ̍�i�͂ЂƂ̔�g�̑��u�ł����āA�����Ɂi�ǎ҂́j���̂�̍��߂āA�����̖������邱�ƂɂȂ�v
�����炭���̖��͈������ł���A�������́A���l�����ł͂Ȃ������������\�������Ă����^����ڂ̓�����ɂ��邾�낤�B�{���Ɍ��������o����̂́A�X�������̊W���͂����āA�ۉ��Ȃ��˂����邩��ł���B�G���O���Ƃ������낷���Ƃ͗e�Ղ��B�����A���R�Ƃ����ɂ���A�f�ʂ�ɂ͂ł��Ȃ������ɁA�����������Ă��邨�̂���F�߂���Ȃ��̂��B�ȉ��Ɂu��g�̑��u�v�����B
���z�͊��݂͂��߂��̂ɁA�݂ɓ˂��h�����Ă���X�Ђ͂����ς�Z���Ă��ꂻ���ɂȂ��B
���T�C�����̉����Ƃ������B�����肪�����@�B�L���A�ǂ����V��������ɂ߂��荇�����炵���B
���k�������D��S�̃}�X�N������ƁA�l�Ԃ͂߂��ꔽ���āA���Ԃ��̑��l�ɂȂ�B
���ዅ�������ς��ɖj�����đO���������ł��͂��߂Ă����B
���g�}�g�̔�̂悤�ɒ��������Č�����A���C�ł����͂��Ȕ��������B

�w�J���K���[�E�m�[�g�x�@�����@���[
���[�����a���ɏ����グ���A�Ō�̒��ҏ����B�S�҂ɎU��߂�ꂽ���m�����A�ǂ������Ȃ��d�ꂵ�����Y���A����܂ł̍앗�Ƃ͂܂�������育����������������B����̃h�i���h�E�L�[�����̌������A�u����͎������ł���v�B���̎��ȗ�����ь������Ă����j���A�Ō�̍Ō�ɂ������߂����̂����A����Ȃ��������I�ł������Ƃ����������́A����Ƃ��������悤���Ȃ��B
���钩�ˑR�A�j�����Ɂu�J�C�����卪�v�������Ă���Ƃ����A���[�Ȃ�ł͂̊�z�͂����ł����݂ł���B�Ƃ͌����A���̖{����Ɏ���Ĉȍ~�A�J�C���������������œf���C���Â��ǎ҂�����قǂ�����A�����Ă��ꂢ�Ƃ͌������������X�����`�ʂ��l�����̂��B�ǂ��ɂ��A�C���[�W�I�����̖тƃJ�C�������������ėǂ��Ȃ��B�������Ȃ���A�u���̉������ɋa�������͂������v�Ƃ��������̍Ⴆ�͌����B�����āA�����҂���������x�b�h�Ƃ������z�����j�[�N�ŁA�ނ̈�˂͟����ǂ��납�A�܂��܂������Ă���悤�ɂ����v����B
�̉͌����o�R���A���ɏ�����߂ĕs�C���ɂЂ�����x�b�h�̗��ŁA��l���́A����l���Ǝv����O�l�̏����Əo��B�u��̒����A���܂ɂ����ڂꗎ�������ȉ�����ځv�̏������B�g���{�ዾ�̊Ō�w�i�̌�����̃h���L�������j�A�~�j��Ԃɏ���Ă��������A�u�������N���u�v�̏W�����̏��S�c�B�����͓����Ȃ̂����A�������������l��������A�l�ԂƂ����������X�Ɏp��ς���S�t���̕����̂悤�ȏ����A��l���̍Ō���Ŏ��Ƃ����؏����ɁA���[���g�̊�]���ǂݎ���悤�ŋ����[���B�����āA�����Ɏ����āA�^�̔����҂͔ޏ��ł������ƋC�Â������̂��B
���o�̕Г��ؕ�����ɁA�V���n������悤�ȓW�J�B�Â��\���ɏ[���������[�S�[�����h�A�Ƃł������ׂ����B�Ō�܂Œo�ɂ��邱�ƂȂ���C�ɓǂ܂���͍�ł���B�������A��\����A�O���ǂ�ŁA�ޓ��L�ً̈�Ԃɓ����ł����Ɏ��Ȃ��ƁA�ŋC�ɓ��Ă��邾���ŁA���̂悤�ɏ�܂ꂽ�[�w�܂Ŗ��키���Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B

�w������]�x�@�C�V��@�v
�t�B�N�V�����ł���Ƃ��Ȃ���A���f���ƂȂ����l���̎����Ɍ���Ȃ����܂�����B�w�����h���̂��߂Ɂx�w�ēx�ł��̕M�͎͂��؍ς݂ł��邪�A�{���͗����E�̋����A�Ґ×Y�̔����������ɕ`�������Ă���B
�V���L�҂��璲���t�w�Z�Z���ւ̓]�i�B
�Ґ×Y�́A�t�����X������������ׂ��l�ނ��F���ɓ��������̓��{����A���m�̖������߂ĉ��Ăɗ������Ă䂭�B
�T�ڂɂ͐H�ׂĂ���̑A�܂��������A��������́u�H�ׂ�v�Ƃ����y���݂����������s�ɑ��Ȃ�Ȃ������B���ł����O�����u���A�����З��������Ă͂₳��Ă��邪�A�ވȑO�Ƀt�����X�����͂Ȃ��A����̕S��㇗��Ԃ�́A�ނ�������ƌ����Ă������낤�B
�{���͑�ꋉ�̋��珑�ł���ƂƂ��ɁA�����ւ̃n�E�c�E���Ƃ��Ă��y���߂�`�L�����ł���B
�u����b���q�̂�����ׂ�N�b�L���O�v�u�����`�̏����v�u�ǂ����̗����V���[�v�A�Ғ��O���[�v���肪�����ԑg�͂܂��܂����m��Ȃ��B�ނ���ďグ���ق�̈�[�ł���Ƃ������Ƃ������Y���Ă����B

�w�����َE�l�����x�@���I�@�����Y
�\�t�B�X�g�w�h���v�킹���k�ق��Ȋw�I�`��B���ꂾ���ň�҂����藧���Ă���ƌ����ĉߌ��ł͂Ȃ��B
���Ƃ��A�v����q�i�}���|��j�Ɩ@���ّ��Y�i�Y���ٌ�m�j�̒��X���~������Ƃ�̏�ʁA�ӂ���̒��l�I���w�Ԃ�ɂ͋�������邪�A����ł��Ă����Ƃ����������Ȃ��A�r�����m�ȗ������������������ɓ]�����Ă���悤�Ȉ�ۂ�����B
�@���̐����́A���x���^���ɋ߂Â��ƌ����Ă͗���A����̐l�Ԃ�f�킹��i焈Ղ�����ƌ����ׂ����j�B�������A���L��̂����ɁA���_�𓊂��o���悤�Ȍ������J��Ԃ����̂�����A���R�Ɠǂݎ�̃C���C��������Ă䂭�̂ł���B
�w�����َE�l�����x�́A��Ƃ�������ł���Ǝ��͎v���B�Ō�܂œǂݐ�R�c�́A�����̖����ɂ͖ڂ��Ԃ邱�ƁA����Ȃ�Ɋw���̂���Ύ����̖�����肾�Ǝv���āA�܂Ƃ��ɓǂ܂Ȃ����Ƃł���B
�����g���b�N�A�����̂ڂ�r���A�������������A���Ղ̋U���ȂǁA���������̃G�b�Z���X���ڂ̖{���ł͂��邪�A�͂����ĕ��w�I���l�ƂȂ�Ƃ������Ȃ��̂��낤�B�]�_�ƊԂŕ]��������Ă���Ƃ����_�́A�w�h�O���E�}�O���x��w�����ւ̋����x�Ƌ��ʂ�����F�ł�����B���͂̕]���͂��Ă����A�����Y�ɂƂ��āA�������������Ǝ��̂����f�I�ȃQ�[���ł���A���t��M�Ԗ��x�ɐZ���Ă����̂ł͂���܂����B
�Ƃ͌����Ȃ���A���̍�i�ɂ͍R������͂�����̂��ے�ł��Ȃ��B�ǂݐi�߂邾���ł����Ղ����Ղ��Ă���_�o���A�܂��y�_���g���[�̍^���ɕ���o�������Ȃ�悤�ȁA����Ȋ���������B�]�ː에���̌������A�u�q�����ۂ��@�\�ł���ׂɁA��̓I�L�q�̏Ǝ˂ɑς����Ȃ��v��i�ł͂��邪�A�����قƂ����ً�Ԃ̍\�z�ɂ͐��������悤���B�Ђ���Ƃ����m�ق̂������܂��ɉ����āA���̂ɕ����яオ������͂�A���n����̓��ȂǁA���̕`�ʂ͖��@�I�Ȕ������œ��ꂳ��Ă���B�o��l���ɁA���̒ʂ����l�Ԃ̉����݂�������ꂸ�A������ɂ����邷�ׂĂ̂��̂��A��҂̈ӂ̂܂܂ɓ��������l�`�ł��邩�̂悤�ȍ��o���o����̂��B�ˋ�ɓO����A���I�Ƃ������͓��R�̋A���ł���B���a�����̍�i�ł���Ȃ���A����I�ȗv�f���F�Z���A����ł��Ē������m�̕��͋C�������o���Ă�����ِ��͒��ڂ��ׂ��Ƃ���ł��낤�B

�w���H�Ɨ��M�x�@�i�n�@�ɑ��Y
�n�c��̎���A�`��������Ɍ��ꂽ����̒����A���H�Ɨ��M�B
��l�̐l���Δ�����邱�ƂȂ���A�e�������̕`�ʂ����̂܂܁A�i�n���l�Ԋw�ɂȂ��Ă���Ƃ��낪�����[���B�`���ɑ��H���Q���A�������⍂�B���H�̑��߂ł���m�b�܂ł���䗑��B�����R�����x���s���������폟���R�A��綂ȂǁA�ނ�̈ꋓ�ꓮ�Ɍ���Ă��\�����A���̕���ɂ��������̐[�݂�^���Ă���B
���M�́A����������Ŋ�Ȃ��������A���肪�v�킸���݂������Ȃ�悤�Ȉ��g�̂���l���B�g����Ȃ�A�l������銰�₩�Ȋ�ł���A���g�͖��ɓ������B�����炱���A��ɎQ�d�ƂȂ��Ďx���钣�ǂ�A�J���A�ؐM�炪�z�����܂��悤�ɂ��Ă��̖��c�ɐg�𓊂����̂ł���B�Ђ⍀�H�́A�E�҉ʊ��ʼnX�����p�Y���̂��́B���炪��̑��݂Ƃ��Ċ������Ă����Ƃ���ɁA�ő�̌��ׂ��������悤���B�{���͏㒆���̎O�����Ȃ邪�i�V�����Ɂj�A���H�Ɨ��M�Ɋւ��Ă͏㊪�łقƂ�ǂ��̐l������`�����Ă���ƌ����Ă悭�A�ނ���S���ɎU��߂�ꂽ���܂��܂ȑ}�b�i�ؐM�̌҂�����A�I�M�̈����ȂȂǁj�ɁA�l�ԂƂ������̂̏\�l�\�F�̂������낳�����o���ł��낤�B�l�I�ɂ́A���ǎq�[�̗圤�ŗ��₩�ȕ��p�ƁA�^�ɂ͂܂�Ȃ����݂Ȕ��z�͂Ɏ䂩�ꂽ�B
����ɂ��Ă��A���܂ꎝ�������Ȃ͗e�Ղɂ͕ς����ʂ��̂炵���B�l�߂̊Â������x�Ђ߂Ă��A���H�͑ԓx�����߂��A䗑��͎����݂������ł������B�u�����������l�Ȃ̂��v�ƌ��_�����\�����ׂĎ��ꂽ���ǂ̇����c���c�@���Ƃ́A�D�ΏƂł���B
���オ�傫���ϓ�����Ƃ��A�m�I�D��S���h������Ĉ�ࣂ��闲�������}����B��Ƃ⓹�ƁA����ɂ͕��ƁA�c���Ƃ�㇗��Ԃ�͂��̍����s�[�N�ł������B���Ƃ����ɂ����Ē��҂́A�㊿�ȍ~�̒m�I��ڂ�Q���Ă���B
�i�n�ɑ��Y�̐��E

�w�`�@�o�x�@�i�n�@�ɑ��Y
����т₩�ȓ`���Ƃ͈ꖡ�Ⴄ�A�i�n�ŋ`�o�����j�[�N�B
�ٌc�Əo�������勴�̈�b���A�ߐ�ł̍Ŋ����A�����ł͕`����Ă��Ȃ��B�R���̓V�˂ł���Ȃ��琭���I�s���ł���A�H��̐F�D�݂ł��������`�o�́A���悻�`���Ƃ͂������ꂽ�l�Ԑ����߂Ȃقǂɕ`�����Ă���B���͈����l�����A�Y�����̂��Ƃ����ɑ���o�����i�n���w�ł͂��邪�A���̍�i�͏��X�َ��ł���B�����̏��S�Ɠi�S�A�㔒�͖@�c�����ςƈ���ȂǁA�l�Ԃ̂���炵�������������L����悤�ȕM�v�́A��O�I�ł�������B�łт䂭�u�����v���犴�������Ȃ��`�o���́A�h��ւ����Ă������j�̐o���s�ׂƎ��Ȃ����Ȃ��B���������Ăق����Ƃ������z���ł͂Ȃ��A�����炭�����ł������ł��낤�p��Nj������{�p�����A�����ɂ͂���悤���B
���������`�o�Ɨ����Ƃł́A���菊�Ƃ��闧���ʒu���܂�ňقȂ��Ă����B���Ɠ����̈ꎖ�ɂ��Ă��A�`�o�ɂƂ��Ă͖S���̓G�����ł����Ȃ��A�����ɂƂ��Ă͊��q�̐���z�����߂̂��́A����������A�V�c�i���j�ƍs����藣���ŏ��̎��Ƃł������B�g�D�̑n�n�҂Ƃ��Ẳ��d�������ɂ͂���A���[�_�[�Ƃ��Ă̎������A�ϊv�҂Ƃ��Ă̎������[�������Ă����ƌ����邾�낤�B�Ђ�A�u����݂͂Ȃ킵�̎w�}�ŏ��������Ƃ��B���̂��Ƃ����q�͂킩���Ă��Ȃ��v�ƁA���e�̏�ɊÂ���������ŁA�R�����ЂƂ��߂ɂ��悤�Ƃ����`�o�̒����́A���̂�̌��������������R�̌��ʂł������B����܂ł̔��X���������͑ł��ӂ��ꂽ���A�l�S��͂ނ��Ƃ̓���A�������̐l�C�⓯����ł͐����c��Ȃ��A����ȕ��m�̐����_�Ԍ����v���ł���B

�w���̒��̎��y�x�@�|�{�@����
�w�����ւ̋����x�ւ̃I�}�[�W���Ƃ��Ē�o���ꂽ�{���B7��12���Ŋ��������w�����c�x�������p���悤�ɁA7��13���̕`�ʂ���͂��܂�A���ꂾ���ł����҂̐S���Ԃ肪�M����Ƃ������́B
�P�A�R�A�T�͂��ЂƑ����̕���ƂȂ��Ă��āA�Q�A�S�͂͂��̌������Ƃ��đ}������Ă���B����䂦�A��͂ŎE���ꂽ�j���A�����͂ł҂�҂Ă��Ă������͂Ȃ��̂����A�ǂޑ��͂��̊Ԃɂ������Ƌ��\�̍I�݂ȖԖڂɈ���������A�����ʒu���������Ă��܂��B�����Ă݂�A������o�߂����肪���̒��Ŗڊo�߂��ɉ߂����A���\�̊C��f�r���悤�ȁA����ȃC���[�W���B���̍����́A�����i�����܂ŏ����̒��̌��������j�ɋN���������𐄗����邽�߂ɁA���������ł���w�����ɂ��Ė����͂���ꂽ���x�����菈�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��炫�Ă���B��s���鏬�����A���������Ƃ���ǂ�������t�]���ۂɁA����������^�I�ȋC���Ɋׂ����o��l�������̎v�l�́A�Ɛl�{�����烏�g�\���{���i�x����Ă���̂͒N���j�ւƈڍs���Ă䂭�B
���ƂȂ�̂́u�l�`�v�Ɓu�������܁v�Ƃ������t�B���Ƃ��A�o��l���́u���ː^���v�i�˂ǂ܂肨�j�v�́A�}���I�l�b�g�������������̂ł���A�u���̕����v�ɏ���ꂽ�l�`�����́A�����ɏW�����g�̐l�Ԃ������A�ڂɌ����ʎ��ő����Ă��邩�̂悤���B�����^�̐l�`�����́A�����̏�����ł���i�C���Y���N�ł��A�ŏ��Ɏ��g�Ԃł��Ȃ��B�ǂݎ�̐S���܂ő���|�{�����{�l�Ȃ̂ł���B
�Ȋw�I�ȗv�f�́w�����فc�x���A�[�w�ɐ��ދ��C�́w�h�O���c�x��z�N������A�}�j�A�ɂ͂��܂�Ȃ�����B�O���̌O����������ł͂��邪�A�W���N�X�̒�Βʂ�A���̏�����͉z�����Ȃ��ǂƂȂ��āA���Ȃ���҂̑O�ɗ����͂������Ă���B

�w�A���W���[�m���ɉԑ����x�@�_�j�G���E�L�C�X
�m��Ȃ��������炱���u�K���v�ł��肦���`���[���[�B��p��m�������ƂŁA�l�Ԃ̓��ʂɐ��ޏX����m���Ă��܂��B
�ŏ��̕��͂̂��ǂ��ǂ����́A���̂܂܃`���[���[�̒Ⴂ�m�\���x���������Ă���B�c�t�ł͂��邪�A�����݂̂���l�������ݏo�Ă��āA�p��̗��m�I�ȕ��͂ƑΏƓI�B����̖ڊo�߂Ɛ��~�̎��o�A���̕`�ʂ������ł���A�s�ׂ��鎩�ȂƂ�������߂鎩�Ȃ̑Λ����A�`���[���[�̐����Ԃ���M�킹��B
�㔼�A�]�̑މ��ɋ����ꂵ�ނ��܂́A���l�ɋ��ʂ́u�V���v�ւ̋��|�ɂ����ċ����[���B�l�̈ꐶ���Ïk�����悤�ȋO�Ղ̖��A���ȐS�����߂����`���[���[�́A�Ō�́u�������ف[�����v���������B
���҂͂�����Ɓc�Ƃ������ɂ́A���̌��`�ł��钆�єŁw�A���W���[�m���ɉԑ����x�i�w�S�̋��x���^�j������̂ŁA���Ј�ǂ�E�߂����B

�w���@���x�@�ҁ@�m��
�u�l�͎���ǂ�����s���Ƃ�납�v�c����͒N������x�͗����~�܂閽��ł���B�������Í������A���������N���K�ȓ��������o�����ł��낤�B
���͑��݂���̂��A�։�͂���̂��A���ւ̔��R�Ƃ����s���A�D��S���A�������ɐ��X�������|�Ƃ��Đg�ɔ���A�S���`�ʂ̖��B
��l���ł���S�C���̍]�����́A�܍̎����߂Đl�Ԃ̎���ڂ̓�����ɂ���B�Α��ꂩ�珸�鎇�̉������߂Ȃ���A���܂ő��݂����҂����ɋA����s�v�c���v���A�����悤�̂Ȃ��|�������B�ނ͂܂��A�����̏����������A�����������̂��n���ŕ������邳�܂�z�����Ă͔ߒQ�ɂ��ꂽ�B�l�͂ǂ����痈�Ăǂ��֍s���̂��A���̖₢�����ɏo���݂͂��Ȃ��B
��n�ł̋Ɍ��̌��A����̎��A�e�F�̎��E�B�����̎��ɐڂ��A�₪�ĘZ�\�Z�ɂȂ������́A�����̎��҂����̍��Ŕ�������邱�Ƃ��v�����̂����c�B �ߋ������l�A�������悤�Ƃ��Ă���l�A�F����ɂȂ邱�ƂŁA�����̍����ɉ�A����̂��l�Ԃ̍K���ł���Ƃ����A��ғƓ��̃��b�Z�[�W�����̒ꗬ�ɂ���B�w�s�A�j�V���x�w��Ȃ��ƕ��Ȃ鎞���x�Ƃ��������̍�i�Ɣ�ׂ�A��i�Ɛ[�����n�̊�����B
�P�X�X�X�N�x�t�F�~�i�E�G�g�����W�F��܁B

�w�����ւ̋����x�@����@�p�v
�w�h�O���E�}�O���x�i����v��j�A�w�����َE�l�����x�i���I�����Y�j�ƕ��ԓ��{�O���̂ЂƂB
���܂��܂ȐF�ʂ̃��F�[�����A���̍�i���d�|���̖�����S���Ă���B�܂��͎E�l����ƂȂ����X���Ƃ̕����i�Ԃ̕����A�̕����c�j�A�o��l���̖��O�i�������A�g�i�A���i�A�Y�c�j�A�ڍ��s�����n�߂Ƃ���ܐF�s�����N�B���̉Ԃɂ͐E�ԁE���̎O�F���������Ƃ͂Ȃ��Ƃ������R�E�̖@���B�����Ēa���B�ǂݐi�߂�ɂ�A���F���m���Ԃ��荇���A�����������Č݂��ɓł�f���o���Ă���悤�ȁA����ȕs�������o���邱�ƂƂȂ邾�낤�B
�g���b�N�ƕ����Í��̗��s�C�����B��]�O�]�ǂ��납�A���x���ϗe���鎖���̑S�e�B�H���ł����Ղ��o���������A��҂͂ǂ����Ă����܂ł���K�v���������̂��B�ǂ���炻���ɂ́A����p�v�Ɠ��̇��܂݇�������炵���B�Ō�̂�����ŁA�g���b�N������������A����Ƃ���࣏n���̋�������V�тɑ��Ȃ�ʁA�Ƃ����咣�������яオ���Ă���B�����̔ƍ߂͂����Ɣ����ŕ��G�Ȃ��́A�َ��Ȃ��̂ł����āA���y�I�Ŏ�I�Ȑ��������Ȃ́A�قlj����㕨�Ȃ̂��Ɣނ͌��������̂ł���B�܂�͐��������̃A���`�e�[�[�Ƃ��āA�����܂ŃM�g�M�g�ɓh��ł߂�K�v���������̂��B�����������Ƃ��č����o���ꂽ�{���A����ԈႦ�Ƃ�ł��Ȃ����H�ɖ������ނ��ƁA���������ł���B
�@�u�����v�֕����鋟���ɂƔ����������C�ɗ����ʁi�|�[���E���@�����[�j
�@�w���̒��̎��y�x

�w���~�b�g�x�@���@��
���łɋr�{�ƂƂ��Ċ��钘�҂����������ĕ������A�~�X�e���[�����̈ӗ~��B
�U�����ꂽ�킪�q���~���o�����߁A�K���ɒǐՂ��鏗�Y���L�����q�B���w���t�Ƃ����o��������Ȃ���A�A���U���A���프���Ɏ����߂�⌌�̔����A�V���q�i�B
�q�{�Ń��m���l����Ƃ������i�����j�ɁA�Ƃ��ɏՂ���������Ȃ���A���̐l�Ԑ��͑ΏƓI�ł���B���g�n�w�ƂȂ��ĔƐl�ɔ�����q�ƁA�q���h�������Ƃŕꐫ�����萶���A�������ɐS�̋ύt�������Ă䂭�q�i�̑Ό��V�[���́A�s��Ƃ������ߒɂł�������B
�����炭�f�������ӎ������ł��낤�A���҂̈Ӑ}�������Ȃ����Ȃ����A�e�������߂�o��l�������F�Ȃ��A�N��ȐF�ʂ�����Ă���B

�w���a���x�@��@�H��
�Ƃ��鐸�_�ȕa���B�ӂƂ����{�^���̊|���Ⴂ����A���ʂ̐�����D��ꂽ�l�X������������炵�Ă����B
�R�I����̌��C���A�G�ۂ���̗D�����A�`���E����̐l�̗ǂ��ɐS��������ŁA�O���C���ł��Ȃ��ڗA�d�@�̑��݂ɕ�����o�����B �Ƃ͌����A�����Ă��鉿�l�̂Ȃ��l�ԂƂ��āA�d�@�𐧍ق������Ƃ͐������ł��Ȃ��B
�G�ۂ���ɂ́A���Ԃ���邽�߂����ł͂Ȃ��A�����ЂƂ̗��R���������̂ł���B�a�@�Ŏ��ɒ��ɂ͂Ȃ肽���Ȃ��Ƃ����A�������铮�@�B ���_�ȕa���̑̎���₤�A��҂̂܂Ȃ����������ɂ���B�L�����̂ɊW������悤�ɁA���Ԃ���u������A������ӗ~�܂Ŏ����Ă䂭���҂����B
�u�a�@�͂��̐��݉Ƃł͂���܂���B�n��ɔ�ꂽ���������H�����x�߂�m�ł����Ȃ��̂ł��v�Ƃ����G�ۂ���̎莆���ɁX�����B

�w�C��x�@����@����
�ƒ�Ǝd���̂͂��܂ŋ�シ��A����̒��N�j���ɂ͑傢�ɋ������Ăт����ȍ�i�B�������A���̉��l������́u���f�̍Ȃ𗠐�Ȃ�ĂЂǂ��A�g����������Ƃ���v�ƁA�l���𗁂т����邩������Ȃ����c�B
�d����r�ő����Ă����j���A������ӂƗ����~�܂�ƘV�������������܂ŗ��Ă���A�������c�������Ƃ�����悤�ȁA���̂܂܂ł悢�̂��Ƃ����ő����ɂ�����B����߂��悤�ɖ������肽�ӔN���A���邢�͊D�F�̘V�c���B�s�o���ȑ��q�ɁA�Ђ�₩�ȍȁA�{���̎�l���V���q�́A�h�����Ȃ��獡�̐����𑱂��邱�ƂɁA���W����v�������������Ȃ������B�Ƃ͌����A���c�������Ƃ��F�������Ƃ����̂��A�[���̂����Ȃ��b�ŁA�V���q�ɂ͂����ƁA�d���œ���������Ăق��������悤�ȋC������B
���͓����A�V���q�Ƃ�������S����������肾�����Əq�ׂĂ��邪�A�������̂悤�Ȍ����Ȃ�A�܂�ň�����nj㊴��������ł��낤�B�֊���j�������̂ɂ́A�^���Èł̍s�������҂��Ă��邾�����Ƃ����A�~���悤�̂Ȃ������ɕ���ꂽ��i�ƂȂ����ɈႢ�Ȃ��B���������ۂɂ́A�Ȃ�Ƃ��]�˂��甲���o���āA��l�Ŏx�������Ȃ��琶���Ă䂫�����ȁA���邢�]�C���c���Ē��߂������Ă���A���̂��Ƃɂ���āA���̏����͉��i�ƂȂ蓾���悤�Ɏv����B
�V�����Ƃ�_����i�n�ɑ��Y�ƁA�s��̐l�X��`����������ɂ��ẮA�悭��r�����Ƃ��낾���A�Ђ�u�����҂̕��w�v�ƌĂ�A�Ђ�u���s�҂̕��w�v�ƌĂꂽ�A�������̎����̈Ⴂ���ӎ����Ȃ���ǂݐi�߂�̂��������낢���낤�B

�w�䂵����x�@����@����
�u���ˑR�A���㏬���̎������サ���v�Ƃ͊ےJ�ˈ�̌��ł���B�v���ɂ���́A�i�n�ɑ��Y�A��������Ƃ����A�܂������َ��ȓ�l�̏����肪�o���������ƁA���̈ꎖ�ɐs����̂ł͂Ȃ����낤���B
���̕З���S����������̑�\��w�䂵����x�B�܂��A�l���z�u�̃o�����X�̗ǂ��Ɋ��S��������B���^��r�ȕ��l�Y�A���̂ɒ������핽�Ɗw�Ҕ��̗^�V���B���i���������قȂ�O�l�̗F������ɁA���X�����Q�̂悤�Ȗ��ӂ��A�ǖقɒ��`��S�������`�����A�▭�̃L���X�e�B���O���߂��点�A�s��p�Ȃ�����������������Ă䂭�N�̎p��ǂ��B
�����͂Ȃ�ƌ����Ă��A���̈�[����������ʂł���B�O�ڂɔ������Ȃ��A�����Śb���Ȃ���Ԃ��������l�Y�B���J�Ǝ������Ȃ��܂��ƂȂ��������͐����Ēm��ׂ��ŁA�Ǎ��Ƃ������ׂ��A�e�ɉ��ǂ��Ă���B
�˂̐��p�����A�匠�����ɁA���̏C�s�𗍂߂āA��ׂ����������Ȃ������悤�ȕ����͂������A��B��̕�����Ƃ���B�����N�����o�āA���ӂ��Ƃ̍ĉ�i�����j���ʂ������Ō�̂�������A�����炬�̒��ׂɂ������A�����Ƃ�Ƃ�����Ɉ��Ă���B
����ŏH�R�x���q�ׂĂ���悤�ȁA�����I�ߑ㕶�w�̃C���[�W�́A�c�O�Ȃ��玄�ɂ͊������Ȃ��B�Ǐ��̌����܂��܂��s�����Ă��邩��Ȃ̂��B�ēǁA�āX�ǂɂ���āA���邢�͑��̓����i�ɐG��邱�Ƃɂ���āA�͂��߂Č����Ă�����̂Ȃ̂�������Ȃ��B
�֑������A�C��i���Ȃ����j�ˁA�܊Ԑ�A���쒬�ȂǁA�����̒n���͂��ׂč�҂̑n��ł���B��҂͖����̍˂��������킹�Ă���炵���B�A�܂�������B
�����ЂƂ]�k�B�R�`���̓����������w�ŁA����Ƃقړ������Ɋw�l���ɁA�ےJ�ˈ�A�n�����ꂪ����B
�ےJ�ˈ�I���

�w�O�������q��c���^�x�@����@����
�B�����ĂȂ����肩��K�v�Ƃ���A����ɂ�����l���B�����Ă��̏ꍇ�u����ꂪ�������܂�����A�ǂ�������Ƃ��������c�v�ƓB���������̂��I�`�ł��邪�A�����͐����́A����܂Ŕ|���Ă����o���Ɨ�ÂȔ��f�͂̎����A���ܘV���̎₵���ɗh��Ȃ�����A�������肵�������ŕ���ł䂭�p����ۓI�ł���B
�I�X���K�̒�N����v���`���������A���邱�Ƃ��Ȃ��C�͂������A�{�P�̈�r��H��Ƃ����b���悭�����B�l�Ԃ̐����ɂ����ŏI���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A�����K��邻�̂Ƃ��܂ŁA�͂�s���Đ��������Ȃ���Ȃ�ʁi���t�̌��j�ƁA��҂͖{����ʂ��ČĂт����Ă���B�����Ŕ��g�s���ƂȂ����F�l�������A�����K�����n�߂��Ƃ��A�����������Č�����Ă��������B���̉����Ȃ܂Ȃ����͂��̂܂܁A����������ɑ���ꂽ�G�[���Ǝ��悤�B���̂�̕s�����t���݂������䉜�V���A���͂ɖ��������Ղ�Ȓ��c�ƘV�A����畉�̐l�����́A����ԈႦ�ΒN�����Ƃ闎�������������Ă���悤���B�u�l�\���z������A�����̊�ɐӔC�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������t���ӂƂ悬��B�ǂ̂悤�Ȑl�������ł������A���̐l�̒��g���N��ƂƂ��Ɋ�ɕ\���ƌ������A��l���Ƒ��̓o��l���́A����̂��Ƃ��e�i�����j�̑���ɁA�ǂݎ�͓��h���o�����ɂ͂����Ȃ��B

�w�e�����X�g�̃p���\���x�@�����@�ɐD
���̂Ƃ͌����A���������Ɋ������܂ꂽ�ߋ������A�A�����o�[�e���_�[�B�V�h���������ŋN�������e�e���ɂ���āA��\�N�Ԃ̕�������Ă䂭�B�w���^���S�����A���̓��哬�����o�b�N�ɓW�J�����A�e�r�A�K��A�D�q�̎O�p�W�����߂����B
��������Ȃ��\�͍s�ׂ̓e���Ƃ͌ĂȂ��B���ꒆ�̓�̔����������e���ƌĂт��邩�ۂ��A�傢�ɋ^��ł���B
�܂��A���R���d�Ȃ�ɂ��Ă��A�쒆�̌��ƂȂ�l�����A���̓����̎������̏ꏊ�ɂقƂ�Nj����킹��Ƃ����A�����ɂ���蕨�߂����Z�b�e�B���O�͂������Ȃ��̂��B�t�B�N�V���������炱���A���A���e�B��厖�ɂ������B���[�v�������G�������Ƃ��Ȃ��j���A�����Ȃ�p�\�R���̃l�b�g�������ł��邾�낤���B����������̐ݒ��1993�N�AWINDOWS95�ȑO�̑���͎���̋Ƃƌ����悤�B�����ėD�q�̖��A���q�B����قǂ��Ȃꂽ21���A�ʂ����Ă��̓��{�ɋ��邾�낤���B�������畂���яオ��ʉe�́A�ǂ����ς����Ă��O�\�O��B�d���̋������悤�����A����Ĉ�ɂ����ӂ��������̂��B���A�����̓�ɖڂ��Ԃ�A���������䂫����M�͂͂������ɁA�����܁E���؏܂̃_�u����܍�i�ł���B
��҂́A��ɂǂ̎���ɂ����Ă��A���̂����C�����ė]���B�����̎u�m������A�w���^��������B����̎�҂��A���̌��C���ǂ��Ɍ����Ĕ��U������̂��A�ǂݐi�߂Ȃ��炻��Ȃ��Ƃ��C�ɂȂ�������ł���B

�w�ĕP�t�H�x�@�{��J�@����
���������̑̓��ɏh���␢�̔����A�ĕP�B�ޏ��̔����ɐG�ꂽ�j�́A�c�炸��Ƃ̎��𐋂����B����͌Ñ㒆���B�_�X�̐��ɋg����₤�A�A�j�~�Y�����F�Z���c���Ă�������ł������B���ꂽ�^���ɁA�|�M���ꑱ�����ĕP�̏t�H�i�N���j��H��B
�����̒j�������A�_�X�����܂ł̔��e�ɘf�킳���Ȃ��A�ЂƂ�ސb�����͈���Ă����B�u�Ƃ���ŁA���Ȃ��͂ǂȂ��ł����v�ƁA�ĕP�̌��Ɍ����B�ꂷ�鐴���ȓ����ɌĂт�����ސb�B�ނɂ��A�j�����͉ĕP�̊O�e���������ŁA���̐S�����悤�Ƃ��Ȃ������A���̐S�����������������A�ĕP���~���邽���ЂƂ�̒j�ł���A�Ƃ����̂ł���B���Ȃ�̎����ꂾ���A�ނ̐[�d�́A�����ĔM�ɕ������ꂽ���̂ł͂Ȃ��A��ÂȎv�l�̒����琶�܂ꂽ���̂ł������B
�ސb�i�ӂ���j�̂ӂ́u�ށv�i�݂��j�A�_�Ɏd����A�Ƃ����ӂł���B�ނ́A���܂ꂽ�܂܂́u鮁v�i�A�j�̏�Ԃł���ĕP�𐴂߁A�u���v�i�z�j���h���V�����{���B�����������ݍ��݁A���āA�{���ɏ������Ƃ��Ȃ������ޏ��ɁA���߂Č���P���݂������B�ĕP�̎��E����A�����ԗ����U�߂Ă����É_���������u�Ԃł������B
�H��̈����ƕ]���ꂽ�ĕP���A����قǂ���₩�ɕ`����������i�́A���܂ő��݂��Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B���j�̒�����`���ɁA���҂͊����Ē��݁A�����Đ������Ă���B���Ղ͐W�A�^�A�A�A�Ƃ����́A��Ƌ삯�����̕`�ʂɑ����̎��ʂ���A�ĕP���炩�����ꂽ�������邪�A������u�X��v�ł��邪�䂦��̔g��̑傫���ƁA���߂ł���B�ǎ҂̑z���͂��h�����A�j���ɂӂ���݂�����������j�����́A�v���̂ق����Ȃ��B�{���́A���̐����Ȃ������̈���ł���Ɗm�M���Ă���B

�w�����̓�A���z�̐��x�@����@�t��
�w�˂��܂����N���j�N���x���a������ߒ��ŎY�ݏo���ꂽ�A���Y���I��i�B�w�˂��܂����x�̕����͂��u�O�Ȏ�p������݂����ɐ؏������v�i����j���̂ł���ɂ�������炸�A�Ǝ��̐l�i�����L����Ɏ������{���ƁA�{�Ɓw�˂��܂����x��ǂݔ�ׂĂ݂�̂��ꋻ���낤�B
�Ў�ł킪�܂܂ȂЂƂ���q�ł��邱�ƂɁA�����̈����ڂ�����Ă�����l���n�W���N�ƁA�ܔN���̏I���ɓ]�Z���Ă������{����Ƃ̏o�����A���̕���͎n�܂��Ă���B���܂���r�������A�n�W���N�ȊO�A��l�̗F�B���������Ȃ��������{����B�Ђ�A���Ƃ��ĂƂ�Ƃ߂��Ȃ����A���炩�ɉ��������@���Ă���n�W���N�B���̓�l�̋��ʍ��́A�u�ЂƂ���q�v�ł���u�����v�ł������B�ނ̇������������ĕ\������Ȃ�A�����I�ȕ����ɑ��鎷���S�̂Ȃ��A�������̊��A�����āA�����̊���ɂ͋ɂ߂Ē����ł��锽�ʁA���҂ɂ͖��C�Ȃقǎc���A�Ƃ������Ƃł��낤���B
��\�N���̍Ό��A�ނ͓��{����ɌŎ���������B���̊ԁA������ʂ�߂��Č������������A�C�Y�~��C�Y�~�̏]�o�̋L��������ɒu������ɂ��Ȃ���B�������A���炵�������S�Ɏ������A�S�[�̂悤�ȃC�Y�~�̉\���A�ނ̐S�͔������a�ݎn�߂�B����܂Ŏv���o�����Ƃ����Ȃ������C�Y�~�̌��e���A�֊s�Əd�݂������Ĉ����|����A�v���܂܂ɐ����邱�Ƃ͂��Ȃ킿�A�N���������邱�Ƃ��ƋC�Â��B�C�Â�����ł���ɁA�ȗL�I�q������̂Ă悤�Ƃ���g���肳�B�Ȃ������Ă͂��邪�A�����̌����߂�ׂ����݂ł͂Ȃ��Ƃ����킪�܂܂ȗ������A���{����̎��H�ŋ�]�B���ǂ͗L�I�q�̂��ƂւƖ߂��Ă䂭�B
�Ƃ茾���`��A���������҂Ƃ̌�M�͂��ǂ���ǂ�̃n�W���N���A�u���O�v�ɂ��R�~���j�P�[�V�����i���I�ȈӖ������Łj���m���ł����̂́A�C�Y�~�Ɠ��{����̓�l�����B�ޏ������̐��M�A���̃G�l���M�[�݂̂��A���炩�̕ω����n�W���N�ɂ����炵�A�ނ���������˂����������Ƃ��\�ł������B���{������n�W���N�̕��g�A�C�Y�~�𓇖{����̑�p�A�_�~�[�ƍl����Ȃ�A�n�W���N�����{������C�Y�~�Ƃ������������藧�B�{���͎����̈ꕔ�ł���ׂ����́A���������Е��i�������j�����߂�s�ׂ́A���Ƃ�����莩�Ȋ����ւ̓����ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��͂��ߑ����̏��������́A���e��Ȃ��ʂ̌̂ł����āA�ނ̑ɂɈʒu����B�����炱���A�������������A�厖�ȑ��݂Ƃ��Ȃ肤��B�C�Y�~�͂��Ƃ��Ƃ���ȏ��������̈�l�ɉ߂��Ȃ��������A�n�W���N�ɂ���đ傫�����Ȃ��A������鑶�݂ƂȂ����B����ΔނƓ��ɂ́A�����瑤�̐l�ԂƂȂ����̂ł���B�p�����������{����A���̂�̉e�̂悤�ȃC�Y�~�B�n�W���N�͉i���Ɏ����̕Е��������Ă��܂����̂��B
�u�����̓�v�ɂ́A�S��鉽�����҂��Ă��邩������Ȃ��B�����u���z�̐��v�ɂ́A�����̏I����������L�������B�u���z�̐��v�̐Â����ƕ����B����͉���������ł��܂������̌�̐Â����ɑ��Ȃ�Ȃ��A�ނ͂��̂��Ƃ��[���ɔF�����Ȃ�����A�N�����̂̐����܂ŁA������ۂȎ�����ێ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�w�X�v�[�g�j�N�̗��l�x�@����@�t��
���H�ƎO�p�W�A����t���ɂƂ��ďd�v�ȓ�̃��`�[�t�������ɂ���B�w�m���E�F�C�̐X�x�ł̖l�ƒ��q�ƃL�Y�L�A���邢�́w�I���p�C�x�ł̏~���ƍ��Ə���q���A�����ł̂ڂ��Ƃ��݂�ƃ~���E�A�ƍl����������낤�B�������̎O�p�`�́A�ǂ̑g�ݍ������������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�ڂ��͂��݂�ɍD�ӂ������Ă��邪�A���݂�͓����ł���~���E��~���A�~���E�͂���o�����ȗ��A���Ƃ������̂���؎��Ȃ��B�܂�A�݂��̖���ݍ������Ƃ̂Ȃ��O�l�Ȃ̂ł���B
�ϗ��Ԃɕ����߂�ꂽ�~���E���A�����ň���Ȑ����ɂӂ��鎩�����g�i�h�b�y���Q���K�[�j��ڌ�����Ƃ����A�ُ�ȑ̌��B���ꂪ�~���E�́u����o�����v�Ȃ̂����A�ȗ��A�ޏ��̓��̂Ɛ��_�́A������Ƃ�����ɕ������Ă��܂��B�~���E�����������ۂ���̂̓��X�r�A�����������邩��ł͂Ȃ��A������̐��E�̃~���E���A���~���������������čs���������ł͂Ȃ��낤���A�Ƃ��݂�͍l����B�����Ă��钩�A������̐��E�̃~���E�����߂Ă��݂�͏������B
�ŏI�͂��ǂ��ǂނ��B���݂�͖{���ɂ�����̐��E�ɋA���Ă����̂��낤���B�\�ʏ�͂���ȕ��͋C�������o���Ă��邪�A�ǂ����Ⴄ�悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�u�ڂ���͓������E�̓����������Ă���v�́u�������E�v�Ƃ́A������̐��E�Ǝ�邱�Ƃ��ł���B��˂̑��ǂ����蔲�����w�˂��܂����N���j�N���x�ł̉��c�g�I���̂悤�ɁA�ڂ��͂�����̐��E�q����ǂ��A���邢�͖���A�ʉ߂����̂ł͂Ȃ��낤���B�O�������܂ł��Ȃ����A������Ƃ�����̕����ƌ𗬂́A���ハ�[���h�ɂƂ��ďd�v�ȁA��O�̃��`�[�t�ł�����B
�����Ńq���g�ɂȂ�̂��A�쒆�ň��p����Ă��钆���̌Â���b�B���������̌��𒍂��Ȃ���A�u��v�͎�p�I�ȗ͂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���������A���݂�̏��S�ɒu�������Ă݂���ǂ����낤�B�u�l�������ꂽ�猌�͗������̂�v�c�܂�A���݂�͌��̐���ɂ���Ă����瑤�ւ̊�������ɓ��ꂽ�ƍl�����Ȃ����낤���B�����Ă܂��u�ڂ��v���A���݂�̎��H�ɂ���Č��𗬂��A�������ɓ��ꂽ�̂��ƁB
�@�u���ꂩ��ڂ��͎w���Ђ낰�A�����̎�̂Ђ�������ƒ��߂�B�ڂ��͂����Ɍ��̂��Ƃ�T���B�ł����̂��Ƃ͂Ȃ��B����͂������Ԃ�ǂ����ɂ��łɁA�Â��ɂ��݂���ł��܂����̂��v

�w�h�O���E�}�O���x�@����@�v��
�u�����ǂގ҂́A��x�͐��_�Ɉُ���������Ɠ`������A����v�Ƃ���搂�����Ɏ䂩��A�|�����̌������Ŗ{������ɂƂ�l�͈ĊO�����̂ł͂Ȃ����낤���B�������A�N�w���̂悤�ȓ�����ƁA���G�Ɍ�������l�����I��ʐݒ�ɁA���Ȃ�̋����������邱�ƁA�o�傳�ꂽ���B�G���f�B���O�Ŏ�������������A�����鐄�������̑u�����͂��܂���҂ł��Ȃ��B�Ǘ���A�܂��܂�������[�߂邱�ƕK��ł���B
�\�]���͂��̂��l����Ƃ���ɂ��炸�\�@�ł͂ǂ��ł��̂��l����̂��B����͐g�̂��\�������ЂƂ̍זE�ł���Ɩ{���͌����B�זE�Ƃ����L�^���u���\�����ɂ킽���đَ��Ɍ����閲�́A���������狛�ށA��ނւƂ���ꂪ�i�������ߒ��ƁA�l�Ƃ��Ă̓]���̋L���ł���B�V�n�J蓈ȗ��A�זE�ɍ��܂�Ă���������ꂵ�݂Ɗ�т�ٓ��ŒǑ̌����A�I�M���[�ƎY�܂ꂽ�u�ԂɑS�Ă�Y���Ƃ����̂ł���B�ǂݏI���āA���̖{���܂邲�Ƒَ��̖��ł͂Ȃ��̂��A�Ƃ����^�O�ɑ���ꂽ�B�����Ď������܂��A���̂�̌n�������ǂ閲�̒��ɂ���悤�ȁA����ȍ��o���o����̂ł���B
�J��Ԃ����A���̕���œW�J�����]���_�͔��ɋ����[���B���̃G�f���̉��ŃC�u�������̂������T�^���̎ւ��A���W���̋ɂƂ���������Đ��݉B�ꂽ���́A���ꂪ�]�����Ƃ����̂�����A���a�����̍�ƂƂ͎v���ʁA�Ȃ�Ƃ���Ȕ��z�ł���B�]���̓z��ƂȂ��Ă��Ȃ���A�����̈ӎu�ōs�����Ă���Ɗ��Ⴂ���Ă���A�l�Ԃ̃I���f�^���B�S�l�ނ����C�̃T�^��ƌ��������ȕ����ɂ́A��ғ��L�̔�����U��߂��Ă���悤���B���Ȃ݂Ɂu�h�O���E�}�O���v�Ƃ́A����n���̕����Ő؎x�O���V�A���g�������p���w���B�d�����Ȍꊴ����i�S�̂́u�LjÐ^���Áv�ȃg�[���ƂȂ��āA�ǂގ҂������ւƂ����Ȃ��B

���y�[�WTOP��
�Ǐ��m�[�g ������Ƃ̃y�[�W
�������[�@��̐V��
�剪�����w��x�̐��E