砂の女
不条理に馴れてしまう怖さ
昆虫採集に異常なまでの嗜好をみせる教師、仁木順平。彼は誰にも行き先を告げず新種発見の旅に出かけ、とある海辺の集落に辿り着く。砂に埋もれた家に穴居する人々、そこは、砂が人間を生殺しにして飼う、無間地獄のような所であった。男はそのうちの一軒に監禁され、砂掻きの労苦を強いられることになる。何度も脱出を試みては失敗し、いつしか、不便極まりない生活を受け入れる主人公。非日常も、弛まない繰り返しによって日常と化す。慣れてしまえば、不条理も心地良くなってしまうということか。虫にピンを刺し、死の香を放つまでじりじりと弄んでいた男が、囚われて同じような運命を辿るパラドクスは絶妙と言うしかない。
ありえない場面設定。シュールレアリスムに傾倒した公房ならではの特異な世界に、痺れるような陶酔を覚えた。細密な描写と比喩の多用は、慣れるまでかなり読みづらい。が、詩文にも通じるレトリックの巧みさは特筆に価する。以下にその一例をあげよう。
◆渇きが、こめかみのあたりで、破裂した。その破片が、意識の表面にちらばって、ぶつぶつの斑点になった。
◆スコップを手にしたとたんに、折りたたみ式の三脚のように、疲労で骨がずるずると短くなる。
◆一枚一枚、砂の薄皮をむいては流しつづける、風のナイフ。
◆水にたらした墨のように、よどんだ疲労が、輪になり、くらげになり、くす玉になり、原子核模型図になって、にじんでいく。
赤い繭
公房ワールドのエッセンス
四つの寓話的短編。共産主義の影響が色濃く、徹底した幻想世界が、秘められた現実をあぶり出す。
◆赤い繭
教科書にも採用されたことで、公房の作品群ではもっとも有名である。「おれの家が一軒もないのは何故だろう?」という問いに、とんでもない答えを導き出す、逆転の発想がユニーク。肩書を剥ぎ取られた人間に対して、世間の顔という顔が、冷たい壁になる。弾き出された男は足もとからほつれ、やがて、ほつれた糸に包まれる、魂だけの存在となってしまう。肉体と引き換えに、「繭の家」を手に入れた男は、ほの赤く発光しながら、なおも彷徨い続ける。
◆洪 水
ある日、労働者の液化現象が次々生じる。底辺から、上流階級へとそれは広がり、最後は狡猾なノアまで呑み込まれ、第二の洪水によって人類は絶滅する。『赤い繭』ではほつれ、『洪水』ではとろける人間。人体の60%は水だというから、「液体人間」のおとぎ話が、妙に真実味を帯びてくる。上昇志向で登りつめる、現代社会への警鐘か。お山のてっぺんをめざすのはいい、だが、無常という均衡を崩し、流れを堰き止めてはならない。
◆魔法のチョーク
貧乏な絵描きの話。魔法のチョークで、壁にパンやコーヒーを描くと、あら不思議…。子どもの頃、これとよく似た空想をしたものである。しかし、おいしい・満腹・幸せで終わらないのが公房作品であって、いやぁな予感通りの結末が待ち受けている。身体中、壁とチョークの成分でいっぱいになり、ついに壁と同化してしまうアルゴン君。ざらざらと堆積してゆく閉塞感は、『砂の女』を彷彿とさせる。
◆事 業
巨大鼠の量産を手がけたソーセージ工場で、ついに人肉ソーセージの加工が開始された。地球規模で人口増加と食糧不足が進行するという設定。現代が抱える課題と二重写しになって、ブラックジョークと笑い飛ばすことができない。グロテスクな描写の残像は、映像より言葉の方が始末におえないようだ、どうにも後味が悪い。
箱 男
脈絡のない贋魚の夢
人間社会は「見ることと見られること」の不機嫌な関係によって成り立っている。しかし箱男は、「見られずに見ること」を望む、極めて自己チューな存在。はっきり言ってしまえば、見咎められずに覗き見するという、誰もが秘め持つ欲望の遂行者なのである。
この物語の特異性は、まるで夢の世界のように一貫性がないところだろう。まず第一に、贋者を含めて何人もの箱男が登場するということ。「ぼく」は元カメラマンかも知れず、医療を放棄した軍医かもしれなかった。それだけではなく事によっては、「たとえばA」である可能性もあり、覗きを見つけられた少年Dとも考えられ、主人公の実像に迫りたくても、人格を象る輪郭にまるで脈絡がない。これは、雰囲気だけは生々しく残っているのに、人物の顔がどうしても思い出せない、夢そのものの印象に極似していないだろうか。しかも、「ぼく」と贋箱男の会話の中で、次のようなことまでぽろりと口にするのだ。「それを言ったら、あんたたち自身、ぼくの空想の産物に過ぎないことを自分から認めてしまう事になるんだぞ」、この一文をどう受け取ればいいのだろう。「あんたたち」とは贋箱男と看護婦のことを指すのだが、額面通りに捉えるならば、贋者、つまり供述書を書いているCさえも「ぼく」の一部であるということになってしまう。
そして次に上げられることは、時間の観念がそっくり抜けているということである。海辺に干した洗濯物は、塩気を含んで何時間もだらりと湿り続け、箱の中の落書は、どんなに書いてもたっぷり余白が残されている。出口に辿り着いたその一歩が、同時に入り口に踏み入っているという無限循環。読者はメビウスの迷路に、ただ呆然と立ち尽くすしかない。
そんなわれわれ読者のために、公房が与えてくれたヒント。貝殻草の寓話こそ、この小説を理解する上で重要な手がかりと言えるだろう。「貝殻草の匂いを嗅ぐと、魚になった夢を見る」という。魚の形をした拘束衣の中に押し込まれた贋魚は、やがて溺れ死んでしまうのだが、「夢から覚める前に死んでしまったので、もうそれ以上覚めるわけにはいか」ず、贋魚は未来永劫、夢の中に閉じ込められてしまう…。つまりこの小説を、既に死んでいる男の、夢から覚めないままに綴った手記と捉えるならば、すべてのピースが納まるところに納まったパズルように、納得できるのである。
◆ダンボール箱=魚の形をした拘束衣
◆カメラのファインダー=箱の覗き窓=公房の目線
密 会
陥穽にはまった男の閉塞感
「娘の母親でこさえたふとんを齧り、コンクリートの壁から滲み出した水滴を舐め、もう誰からも咎められなくなったこの一人だけの密会にしがみつく」
こう締めくくる結末に、この物語の異様さが表出している。二つの下半身を持つ馬人間、ぶよぶよの生ゴムのような溶骨症の少女、綿吹き病のその母(アカチンと血に染まった緋色のふとん)…胸が悪くなるような奇っ怪な生き物たちが、深層に潜む哀しげな人間の素顔と重なり合う。
失踪した妻を捜す男が、迷路のような大病院の陥穽にはまり、現実社会から消滅するという、公房得意の逆転現象。比較的後期の作品である本書は、変身、消滅、閉塞という彼のモチーフの集大成と言えるだろう。中村真一郎氏いわく、「彼の作品はひとつの比喩の装置であって、そこに(読者は)おのれの魂を沈めて、自分の夢を見ることになる」
おそらくその夢は悪い夢であり、私たちは、他人だけではなく自分さえも欺き続けてきた真実を目の当たりにするだろう。本書に嫌悪感を覚えるのは、醜い部分の蓋をはがして、否応なく突きつけるからである。エログロとこき下ろすことは容易い。だが、厳然とそこにある、素通りにはできない何かに、いつしか捉われているおのれも認めざるを得ないのだ。以下に「比喩の装置」抜粋。
◆額は汗ばみはじめたのに、胃に突き刺さっている氷片はさっぱり融けてくれそうにない。
◆サイレンの音がとだえた。さかりがついた機械猫が、どうやら新しい相手にめぐり合ったらしい。
◆疚しさが好奇心のマスクをつけると、人間はめくれ反って、裏返しの他人になる。
◆眼球をいっぱいに頬張って前頭部が脈打ちはじめていた。
◆トマトの皮のように中が透けて見える、無邪気でちぐはぐな微笑だった。
カンガルー・ノート
自走するベッドとの死出の旅
公房が闘病中に書き上げた、最後の長編小説。全編に散りばめられた滑稽味も、どこか笑えない重苦しさが漂い、これまでの作風とはまた違った手ごたえを感じさせる。解説のドナルド・キーン氏の言を借りれば、「これは私小説である」。あの自己憐憫を毛嫌いしていた男が、最後の最後にしたためたものこそ、限りなく私小説的であったという幕引きは、皮肉としか言いようがない。
ある朝突然、男の脛に「カイワレ大根」が生えてくるという、公房ならではの奇想はここでも健在である。とは言え、この本を手に取って以降、カイワレを見ただけで吐き気を催す読者もいるほどだから、けしてきれいとは言いがたい生々しい描写も考えものだ。どうにも、イメージ的に脛の毛とカイワレがつきすぎて良くない。しかしながら、「脛の下から上に蟻走感がはしった」という導入の冴えは見事。加えて、同伴者が自走するベッドという発想もユニークで、彼の井戸は涸れるどころか、ますます漲ってくるようにさえ思われる。
賽の河原を経由し、死に場を求めて不気味にひた走るベッドの旅で、主人公は、同一人物と思われる三人の女性と出会う。「切れの長い、いまにもこぼれ落ちそうな下がり目」の女たち。トンボ眼鏡の看護婦(採血が趣味のドラキュラ娘)、ミニ列車に乗っていた少女、「お助けクラブ」の集金役の小鬼…。特徴は同じなのだが、少女だったり大人だったり、人間というよりも時々に姿を変える粘液性の物質のような女が、主人公の最後を看取るという筋書きに、公房自身の願望も読み取れるようで興味深い。そして、ここに至って、真の伴走者は彼女であったと気づかされるのだ。
死出の片道切符を手に、遊園地を巡るような展開。暗い予感に充ちたメリーゴーランド、とでも言うべきか。最後まで弛緩することなく一気に読ませる力作である。ただし、代表作を二、三冊読んで、彼特有の異空間に馴染んでから手に取らないと、毒気に当てられるだけで、襞のように畳まれた深層まで味わうことはできないだろう。
他人の顔
顔は他者との通路
素顔がすでにありのままのおのれではなく、一つの仮面である現代人の闇に迫る。
液体空気の爆発によって、顔一面に蛭のようなケロイド痕ができた男。人々の目には、包帯をぐるぐる巻きにした異物としか映らず、街を歩いても目には見えない境界線がいつの間にか彼を弾き出してしまうのだった。これまでと何ひとつ変わらないようでいて、すべてが一変した日常。「顔」という、人とのコミュニケーションを図る入り口をなくしてしまった、ただその一事によって。そして何より、彼の傷口に塩を擦り込んだものは、かけがえのない妻の拒絶であった。精巧な仮面を被ることで、他人との通路を取り戻そうとするのだが…。
結果から言えば、男の試みは無残な失敗に終わってしまう。仮面製作にかけた一年間の努力も、「あなたが仮面の扱い方を知らなすぎただけ」と一蹴される顛末。当初は自分を取り戻すために作られた仮面ではあったが、自分が自分に嫉妬し、支配し支配されるという一人芝居の末に、仮面をつけても何も変わらない素顔のおのれをまざまざと突きつけられる。結局、「顔」は一枚の薄い皮に過ぎず、その顔を再生しても、人間の本質までは再生できないということなのか。道化を演じるのは構わないが、演じていることに無自覚な道化にはなりたくないと綴っていた主人公。待っていたのは、最も避けたかった道化の茶番劇でしかなかったのである。
彼の失敗は、極端なマイナス思考と女性心理の無理解によるものであった。女性の化粧にしても、彼の論理からすれば素顔の否定であって、素顔をより惹きたてるものという受け取り方はしない。それでいながら、仮面を被るだけで相手の心を取り戻せるという短絡思考。とどのつまり、彼には自己変革の素質が皆無であり、「尻尾をくわえた蛇のような長ったらしい告白」を書くぐらいの才覚しかなかったということである。それにしても「おまえ」の最後通牒は、的を射ているだけに手厳しい。
デンドロカカリア
同病者の火を守るプロメテウス
ある日突然、デンドロカカリアという植物に変身するコモン君。
コモンとはすなわち、common、共同、共有という意味である。植物に変身する病が、自分ひとりに起きた異変ではなく、「一つの世界と言ってもよいほど、すべての人の病気」であると悟り、彼はその運命に甘んじて従おうとする。個人という浮き草のような存在から、しっかり根を張って生きる「一員」になるまでの不安と抵抗を表現した作品。
「不幸を取除いてもらったばかりに幸福をも奪われることであり、罪から解放されたかわりに、罰そのものの中に投込まれること」
組織、集団に所属することで、生活は保障されるが、その安心料として、さまざまな拘束を受ける社会というものの構図を、寓意をもって描いている。茫漠とした廃墟の心から救われて、同病者の火を守るプロメテウスになろうとしたコモン君。肝を差し出す代わりに、青々と茂った葉を差し出すつもりなのであろうか。この火がなんであるかは、この場合問題ではない。守るべき何かを持ち得たこと、使命の自覚こそが重要なのである。
コモン君を、将来の青写真もできていないモラトリアム人間、アルピイエを、会社の人事担当に置き換えると、実にわかりやすい。この作品が発表された昭和24年(1949年)は、現代のように簡単に職を変える時代ではなかった。一度帰属したら定年まで、それこそ根を生やしたように会社に尽くす時代であった。そう考えると、やる気のない学生を宥めすかして入社まで漕ぎつけ(コモン改め、デンドロカカリアを植物園に無事植樹して)、しめしめとほくそ笑むアルピイエの心中も、容易に察しがつくのである。
棒になった男
実在への不安 人と物との境界線
『鞄』、『時の崖』、『棒になった男』の三景よりなる戯曲。
公房の創作において、戯曲は重要な位置を占めている。不断に人と物とを混ぜ合わせ、物体との境界を消滅させる試み。現実存在であるところの、人間という前提を覆し、解体するこの試みを、舞台を眺めるように堪能したい。
◆鞄
男は、本皮でできた上質の旅行鞄である。ここでおそらく、誰もが『箱男』を想起するのではないか。角質化した皮膚の物語、かの箱男同様、問題なのは表皮の内側に何があるか、なのである。怪しげにそそるこの鞄を、妻と客の女は開けてみたくてしょうがない。無数の虫が蠢いているのかも知れず、あるいは…。開けた途端に世の中の法則がひっくり返ってしまうことを、彼女たちは予測している。いや、期待していると言ってもいいだろう。現代版パンドラの葛藤。
◆時の崖
ラウンド中のボクサーの、底なしのアンニュイを描いた。チャンピオンの向う側が一番急な崖だとしたら、こっち側は何戦も負け続けるゆるやかな坂である。そのゆるやかな坂を、肉を腐らせながら落ちてゆく。もう死んでいるのに生きている、面倒くさくなるほどの、スローカウント。
◆棒になった男
短編小説『棒』の戯曲版。できれば『棒』と比較しながら本作を楽しみたい。『棒』では、教授と生徒という設定であった立会人が、こちらでは地獄の男女となっている。棒のように誠実に生きた男は、生きたように死んでゆく。とすれば、優柔不断に空っぽの人生を歩んだ人間は、ゴムホースにでもなるのだろう。「棒」が象徴するものはなんであるのか。融通の利かない頑固さ、実直さ、というところだろうか。あるいはもっと、性的な要素も含んでいるのだろう、二組の男女が鍵である。
R62号の発明・鉛の卵
様々な反転 12の方法的プロット
◆R62号の発明
自殺するつもりだった男が、死ぬよりも「生きた死人」にならないかと誘われて、ロボットに改造される話。余計な感情を持たず、組合運動に見向きもしない、純粋に技術だけの機械となった男の末路とは…。血の気も失せるようなおのれの行為に動じないのも、ロボットだから当然である。形容するなら、ふんだんに人間を使役する自動カッターと言うべきか。ブラックな展開がシュール。
◆パニック
パニック商事の就職試験は、指定された場所でひとりの男と会うこと。奇妙な「面接」のあとに、坂道を転げ落ちるような、とんでもないシナリオが待ち受けていた。この世は、目に見えない約束ごとが支配している。その暗黙のルールを破れば、はじき出されるしかない。掌編ながら示唆に富んだ内容に息を呑む。
◆犬
人間のような犬と、誰彼の見境なくじゃれつく、愛玩動物のような女。二者セットで結婚してしまった男の悲劇。
◆変形の記録
射殺された男が、魂だけの存在となって感受した情景の生々しさ。形状記憶シャツならぬ形状記憶亡霊たちの、染み込んだ俗世観がなんとも不気味で、また可笑しくもある。
◆死んだ娘が歌った……
『変形の記録』の少女バージョン。口減らしのため工場兼学校に入れられ、その後、置屋に売られるという、絵に描いたような不仕合せが、物悲しい調べで綴られている。敗戦時の満州を舞台とした『変形…』と対で読まれたし。
◆盲腸
新学説の実験台として、羊の盲腸を移植された男。たかが盲腸ではあるが、一箇所の改変によって、人間ではない何かに変異してしまう怖ろしさを描く。肉体の問題はそのまま、在り方の問題でもあるようだ。
◆人肉食用反対陳情団と三人の紳士たち
食べる側と食べられる側のどこまでもかみ合わない話し合い。食用として飼育された人間はあくまで肉であり、そんな彼らが人権や自由を主張しても、牛のげっぷにしか聞こえない。『家畜人ヤプー』にも通じる徹底した無理解を描くことによって、ブルジョワとプロレタリア、白色人種と有色人種の対立構造を浮き彫りにした風刺劇。
◆鉛の卵
卵形の冬眠カプセルに入れられ、未来にタイムスリップした男。そこでは、食べることが下等生物の行為として蔑まれ、家という観念も存在しない。食べなければ死んでしまうし、食べれば処刑されるという究極のジレンマに、男の下した選択とは…。余談だが、水と光合成しか必要としない緑色の未来人に、ゲームのモンスター、サボテンマンを思い浮かべた。
その他、『棒』、『鍵』、『耳の価値』、『鏡と呼子』など全12編。
渡辺広士の解説によれば、本書は「動物・植物・鉱物を人間と同列に置」いた試作であり、観念と物質、精神と肉体を置き換えた試みでもある。人間が拠り所とするものの頼りなさ、根拠のなさを冷笑的なタッチで描いた、いずれ劣らぬ快作揃い。
燃えつきた地図
閉ざされた無限に地図は要らない
失踪者を探す探偵が、何の手掛かりもつかめないままいつしか帰るべき場所を失い、空白の地図の中を彷徨い始める。これもまた、ミイラ取りがミイラになる、公房得意の手法が生かされた作品。
亭主の失踪も他人事のような、あいまいな印象の妻、胡散臭いその弟、ヌード写真を収集するサイケな元同僚と、都会の闇に蠢く、顔をなくした住人たちの生き様を、ミステリータッチで描いている。登場人物が、誰一人として真っ当ではない。どこか、螺子がイカれた連中ばかりだ。探偵という職業は、事件の糸口を見出すために対話を繰り返すものだが、彼らとの対話は、まさに暖簾に腕押しでさっぱり埒が明かない。くろぐろと口を開けた時空が弟を呑み込み、さらには元同僚を自殺へと導いてゆく。
マッチ箱と古新聞。こんな僅かな痕跡しか残せない失踪者に、誰もがなりうるという存在の希薄さ。限りなくありふれていながら、深層を覗けば、特異な都会の本質が浮かび上がってくる。「閉ざされた無限」である都会に、番地を振っただけの地図など、初めから必要ではなかった。そう悟った主人公(探偵)は、自ら進んで失踪者と重なる道を選ぶ。「贅沢な微笑が頬を融かし」た、その表情に翳りはなく、むしろ晴れ晴れとした予感に充ちていた。
公房はそのエッセイ『内なる辺境』において、「都市という内部の辺境にむかって内的亡命」をはかることを作家の義務であるとしている。他者との対話を諦めて(あるいは進んで放棄して)、自己との対話へと求心的に分け入ってゆく主人公に、そんな公房の姿勢が表出しているのではないだろうか。亡命先で新たな地図を構築するためにも、古いそれは忘れた方が賢明ということなのだろう。
人間そっくり
SF精神の復権
公房の作品をいくつかのジャンルに分けるとするならば、これはSFものと呼ばれる項目に分類される。そしてその同類項として、『空飛ぶ男』、『使者』、『R62号の発明』、『鉛の卵』など、挙げることができるだろう。
自称火星人と脚本家のやりとりが、言葉尻を捉えるやら、揚げ足を取るやら、ばかばかしくも腹立たしい展開。自称火星人は、彼の主張どおり人間そっくりな火星人なのか、あるいは火星人だと思い込んでいるイカれた地球人なのか。かたや脚本家は、「地球病」のせいで、火星人であることを忘れてしまった火星人なのか。読み進めるうちにこちらも混乱し、見えざる手の術中にまんまと嵌る仕掛けとなっている。
相手の狂気を証明しようとすればするほど、おのれの正常性に疑いを深めてゆく脚本家。結局は弁舌にまるめ込まれてしまうのだから、舌先三寸の威力は侮れない。「狂気」というものに、人並みならぬ執着と陶酔を覚える公房ならではの仕掛けが、人間存在の不安定なところをこれでもかと突いてくる。
難解と評される公房作品の中では、比較的読みやすい方だろう。単純化された表層は時にユーモラスでさえあるが、「自分は何者なのか」という問いかけが、その下で混沌と渦巻いている。概念規定を失うということは、取りも直さず存在の輪郭を失うということである。〝そっくり〟な亡者たちはどこへ向かおうとしているのか。「SFが、SF用の檻の中で、いくら豚みたいに繁殖してみせたところで、なんの自慢にもなりはしない。ぼくが夢みているのは、文学のなかでの、SF精神の復権なのである」(SFマガジン『SF、この名づけがたきもの』)という決意にも似た想い。奇矯なストーリーは、ともすると欺瞞の腐臭を放つ。行き過ぎれば、なんでもありの軽業師、虚仮威しのそしりも免れない。そんな危険と背中合わせの試みであったこと、心して読みたいと思う。
◆使者
『人間そっくり』に先行する作品、『使者』についても触れておこう。発表が昭和33年(別冊文芸春秋)と、『人間そっくり』(昭和42年、早川書房)より九年の歳月を遡る。こちらも自称火星人との問答を描いたもので、ほとんど同じような展開。ただ、自称火星人と同行するには至らず、出会いによって主人公の人格に異変が生じた程度で留まっている。
「眼と眼の間がすうっと離れてしまったような…頭が前後に三メートルものびてしまったような…たまらなくいやな気分」と言いながら、何故か明るい表情を浮かべるラストが印象的だ。
空飛ぶ男
仮説的リアリズムの世界
◆空飛ぶ男-笑う月収録版
幻のような夢か、それとも夢のような幻か。ある朝「ぼく」は、腹を下にして魚のように空を飛ぶ男と、目が合ってしまう。
飛ぶ=泳ぐ、飛ぶ⇔墜落の図式に、脱出、逃走という概念を当てはめるのは、いささか早計であると公房は指摘している。そして、因果関係で言えば、飛ぶことはむしろ果でなく因であり、初っ端に飛ばせることが肝要と付け加える。エンディングで飛ばせるという構成は、ある意味作者の放置プレイ。読者は大きな宿題を与えられ、抛り出されたような感覚を覚えるだろう。冒頭で飛ばせることによって、われわれはパニックを共有しながら読み進めることができる。ただし、それはそれで、作者に遠隔操作されているような気分ではあるのだが…。
公房は『死に急ぐ鯨たち』という評論において、次のようなことを述べている。「スプーン曲げを信じないことと、作品の中で登場人物に空中遊泳させることとは、僕のなかではなんら矛盾するものではない」と。つまり、カフカの『変身』のように人間が虫になることも仮説的リアリズムであり、事実として人間が昆虫に変身する世界を創造する、それが文学だというのである。公房もまた、脛にカイワレ大根が生えた男や、ユープケッチャという昆虫を創り出した創造主であると言えるだろう。
この物語のテーマは、「ぼく」を襲う名状しがたい恐怖である。飛ぶ人間を知ったことによる既存世界の崩壊。実を言うと、『笑う月』に収録されているのは、改稿後のものである。自我の破綻をきたすほどの恐怖、というテーマからすれば、改稿前(『空飛ぶ男-周辺飛行9』)の方が、よりエキセントリックでいかにも公房らしい。個人的には改稿前の方が良いと思うのだが、作者なき今その意図を知るよしもない。
◆空飛ぶ男-周辺飛行9(エッセイ)
『空飛ぶ男』の原点であるばかりではなく、それに続く『さまざまな父』、『飛ぶ男』のおおもととなる作品。
「しらばっくれないで下さいよ」→「ごらんになりましたね」、「ほれ、嘘じゃねぇ」→「ほら、嘘じゃない」(→以降が『笑う月』収録版)など、『周辺飛行』の方が荒っぽい言葉遣いとなっている。「ぼく」があまり驚かないことにイラつき、飛ぶ男はついつい喧嘩腰になっているようだ。対する『笑う月』収録版での彼は、なかなかに理性的であり、「ぼく」の反応も鈍い。「君に恐怖感なんて、想像もつかないよ」と、あっさりしたものである。改稿は、ほぼ全体にわたって少しずつ施されているが、『周辺飛行』が即時型恐怖ならば、『笑う月』収録版は追憶型恐怖という雰囲気を醸し出している。「思い出すたびに、心の芯から、汚れた黒い水みたいなおびえ」が這い上ってくる追憶型と、以下の箇所を比較するだけでも興味深い。
「のびきった感情の、切断音。ぼくは反射的に、相手の腕をはらいのけていた。ちりちりと、全身を焼く、おびえの感覚。…糾弾しつづける憎悪の指。…あれ以来、空飛ぶ夢も、いっこうに楽しいものではなくなった…」
◆さまざまな父
父親が箱から取り出した二つの小さなガラス瓶。片方には透明人間になる薬が、もう一方には宙を飛ぶ薬が入っている。くじ引きの結果、父が透明人間、息子が飛ぶ薬を手に入れた…。
父の動静を窺い、薬を飲むタイミングをはかる息子の態度には、今も昔も変わらない父と子の相克が表出しており、一読して、エディプス・コンプレックスの寓意に気づかされる。気配とミントの息遣いだけの父の存在。いるのかいないのか不確かだからこそ、いや増して煙たく威圧的に感じられるのだ。そしてついに、父を撃退する日が訪れる。束縛から解放されたのち、やっとのことで低空浮遊から練習を始める用心深さ。似たような経験、たとえば部屋でこっそり筋力トレーニングに励むなど、誰にでも覚えがあるのではないだろうか。「飛ぶ」はまさしく、飛び越えることを意味している。
「おねえ」を巡る争いに、一条の光りを見出したところで完結するこの物語には、続編がある。「おねえ」は「ぼく」を空気銃で狙撃する狂女となり、父は嫉妬に狂い…。あらたな設定と演出によるセカンドステージ、『飛ぶ男』へと繋がってゆく。
◆飛ぶ男
公房の死後発見された未完の小説。1994年1月に新潮社から刊行されたものには、て、に、を、は、のみならず、多くの箇所に真知夫人の手が入っている。真知夫人の愛情表現と、好意的に受け取れなくもないが、純粋な公房の作品とは言いがたい。とは言え、「飛ぶ男」を扱った連作の一つであることを考慮し、ここに付け加えたい。
『さまざまな父』での「ぼく」は、ここで「マリ・ジャンプ」という名の、スプーン曲げの少年として登場する。彼を狙撃した29歳の独身女性(小文字並子)を巡り、エディプス・コンプレックスの一変形とも思われる感情を、腹違いの兄(保根治)は抱く。塵芥に埋もれて暮らす不眠症の兄。片や、奇術、飛行、透視と、多くの能力を与えられた弟。赤の他人同士であっても、妬むのは当然だろう。『飛ぶ男』の主人公は保根であり、弟の出現によって乱された感情を描いているようにも思えるのだが、後半の歯抜け状態は如何ともしがたく、そこに真意を読み取ることは難しい。
「創作MEMO」を加えると、全部で八種類の原稿がFDに残されていた。つまり、さまざまな段階、違った表情の『飛ぶ男』が存在するということである。公房は、『スプーン曲げの少年』というタイトルにするつもりであったらしい。いずれにせよ、これらをふるいに掛け、校正を重ねる筈であった最終稿は、この世に存在しない。『周辺飛行』に始まり、いくつかのバリエーションで綴られた空飛ぶ夢は、文字通り見果てぬ夢となってしまった。公房の執心を思うと、つくづく残念でならない。
無関係な死
あらゆる所へ行き、どこにも辿り着けない
昭和32年~39年までの足取りのすべて、とあとがきにある。
心づもりでは一貫性があった筈なのだが、まるで行方をくらます犯罪者のような足取りになってしまった、という公房の述懐が、そのままブラックテイストとなって底流に注がれている作品群。
◆無関係な死
仕事を終えて帰宅すると、部屋には見知らぬ男の死体が横たわっていた。濡れ衣を着せられたら一大事と、ヘタな思案に暮れるうちに、時間は容赦なく過ぎてゆく。結局、死体を発見した時点で、警察に通報すれば良かっただけのこと。血痕を拭って染みをひろげてしまうなど、墓穴を掘るだけの行為には呆れるばかりだ。
この設定は前出の『パニック』と似ている。ただし向こうは、採用試験の演出であり本当には死んでいない。出発点を間違えると、それに導かれたゴールも間違いとなる、そんな寓意か。冒頭の「客が来ていた」、「横たわっていた」、「死んでいた」という畳み掛けが効果的。
◆賭
二階と三階の部屋が隣り合わせになるような、奇妙な間取りを依頼された設計士。あまりにもデタラメな注文に首をひねり、依頼主である会社を訪ねるのだが…。
「裸で無人島に行って文明人の服装で戻ってくる」という馬鹿げた企画もすんなり通る、独創性第一のシステム。初めのうちこそ圧倒されていた設計士だったが、次第にその運営方針を受け入れ、同調してゆく。頭脳は常にフル回転。常識を一切排除した思考回路の維持は苦痛でしかない。履き違えられた「独創性」は、やがて大きなひずみとなって襲いかかる。
◆家
代々受け継がれる家宝や家訓。それがたまたま、骨に皺くちゃの皮膚を貼りつけた、ミイラのような先祖であった。
やっかいな代物からどうにかして解放されたい一心で、相続者たちはとうとう「あれ」の始末を決意する。先祖なんてものは幻想にすぎず、実在していないのだから始末しても構わない、という結論に至った兄弟。まるで粗大ゴミを処分するかのような話し合いに聞き耳を立てながら、「あれ」の空洞の眼差しが訴える。この自分が幻想ならば、お前たちの存在も幻想ではないか、と…。
その他、『人魚伝』、『使者』、『誘惑者』、『夢の兵士』、『時の崖』の全8編(昭和39年初版単行本)。
ごあいさつ
こんにちは。Zepkoです。
男性作家のページから、安部公房作品を分離独立させて、新しいサイトを開設しました。
感想文から書評へのグレードアップをめざし、内容の深化と充実を図りたいと思います。
今後ともどうぞよろしく!!
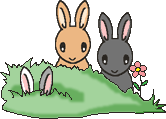
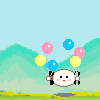
Contents of This site
ページ内リンク
a la carte
安部公房は、遺作がFDに残されていた最初の日本人作家と言われている。
好きな音楽はピンク・フロイド。
趣味は写真撮影。シンセサイザーも所有していた。当時の作家としては、かなりデジタル適応型であったと言えるだろう。

詩人 安部公房
作家、安部公房が生れるためには、詩人、安部公房の抹消は必然であった。
1947年に発行された『無名詩集』は、ガリ版刷りの粗末な装丁ではあったものの、その中身は、しっかりとした骨格を縫ってほとばしる、堂々たる現代詩であった。エキセントリックなだけではない、公房の繊細な資質と、詩的原風景を覗かせて興味深い。その中から、「リンゴの実」の終連部を紹介しよう。
「球体への涯しない内部の途を/窮め得ぬその面(も)の影にさながら/路標(しるべ)なき存在を泣かぬだらうか/君が差出した一つの結実を/今僕は唯明るい夢の様に怖れる/涙も亦一つの球体ではなかつたか」
この詩には、「真知の為に」という献辞が添えられている。ご令室、真知さんに捧げられたもので、二人は『無名詩集』の編まれた年に結婚している。
高等遊民と箱男
『屋根裏の散歩者』郷田三郎は、何事にも飽きっぽく、興味を持続できない高等遊民。安息を求めて押入れに出入りするうちに、天井裏から覗き見ることの悦楽を知るのだが…。この、江戸川乱歩の代表作に、多くの人が公房との接点を見出すのではないだろうか。窃視願望は『箱男』を、押入れに籠もる胎内願望は、同じく『箱男』と『カンガルー・ノート』を彷彿とさせる。
他人の視線から解放され、脱力しきっている人間の滑稽さ。気取り屋の浅ましい実態を、人知れず観察する醍醐味も、高等遊民、郷田三郎にとっては、やがて色褪せてしまうゲームに過ぎなかった。より強烈な刺激を得るために、完全犯罪をもくろんだ郷田と、いつ果てるともなく覗き続け、皮膚とダンボールを同化させていった箱男の違いは、まさにこの点にあるだろう。節穴や隙間から覗く世界に、共に魅せられていながら、一方の箱男は飽きるということを知らない。
高等遊民…明治後期から大正にかけて出てきた、大学を卒業したのに就職出来ない、自分のしたい仕事がないといった若者のことを指す言葉。
母胎への回帰願望
澁澤龍彦がその著書『エロティシズム』において、興味深い所見を述べている。澁澤いわく、「小さな箱は、いわば子宮であり、洞窟や壺や卵のような、内部が空洞になっている物体もまた、すべて子宮の象徴」であって、それらに対して抱く恐怖と魅惑のアンビヴァレンツ(反対衝動)は、かつて棲んでいた母胎への回帰願望に他ならない。航海中、嵐に遭って海へ投げこまれ、鯨に呑まれて三日三晩、魚の腹のなかにいたというヨナ。おそらく『箱男』の原点であろう、ヨナ・コンプレックスは、旧約聖書以来の、根源的衝動と言えるのではないだろうか。
ユーキッタン
「緋色のふとん」(『密会』)で思い出すのが、『詩人の生涯』の真っ赤なジャケツ。綿のように疲れ切った老婆の体で紡がれ、彼女の心臓から溢れ出た血に染まった、かなしいジャケツの物語だ。
レトリック満載、オノマトペの効果的反復は、一編の詩を思わせ(ユーキッタン、ユーキッタン ジャケツ、ジャケツ チキンヂキンと鳴る雪)、痛みが切実な声となって伝わってくる本書。「夢や魂や願望が結晶してできた雪」の白さと、ジャケツとのコントラストも絶妙で、モノクロフィルムに赤だけ加えた、象徴的映像が目に浮かぶ。
さて、この物語の「詩人」について。詩人とはこの場合、息子であり老婆でもある。彼女が「糸になった脳で考え、糸になった心臓で」思い、文字通り〝心血〟を注いで書き上げた鮮烈な詩を、じっくり味わいたい。
ジャケツが必要な人間は、貧しすぎて買うことができず、裕福な人間は赤いジャケツに見向きもしない。『詩人の生涯』は、格差を風刺した告発劇でもある。
カンガルーとベッド
「ぼくの意識のジャンプはカンガルー-跳ねる-スプリング-ベッドによって反復される」とは石崎等の言葉である。
(『国文学』1997年8月号 安部公房ボーダーレスの思想)
ひとつの夢から別の夢へとジャンプする「ぼく」の意識は、自在なワープとはほど遠く、悪夢の範疇から抜け出すことのできない、「贋魚」のように窮屈なものである。意識世界においても、現実世界においても、待っているのは死という終着であることを思えば、この「意識のジャンプ」もあだ花としか言いようがない。
カンガルーとベッドの図式は、さらにもうひとつある。カンガルー-母の胎内-ベッド…母カンガルーの袋の中で安らぐ子カンガルーと、ベッドに戻る「ぼく」の心理は同一と見ていいだろう。ベッドに横たわるひとときが、あの嫌な予感に充ちた、カイワレの繁茂を忘れられる唯一の安息。死出の旅は、幼児へと退行する旅でもあるようだ。
仮面と能面
『他人の顔』の文中に、仮面と能面についての興味深い記述がある。
仮面が正の方向への脱出であるとすれば、能面は負の方向を目指している。容れようと思えば、どんな表情も容れられる空っぽの容器。なるほど、能面の特徴をずばり言い当てている。
また、未開人の仮面のデフォルメ(幾何学模様やビーズ玉で編み上げた鼻など)は、神々に近づこうとする激しい意志の凝縮であると、公房は考察している。『他人の顔』の主人公が、よりリアルな「顔」を目指したのに対し、こちらの仮面はまったく逆を志向するもの。使う側の意図によって、仮面もさまざまということだろう。
Dendrocacalia crepidifolia
デンドロカカリアは母島に生息する樹木の名。和名をワダンノキと言う。

地獄の下層、自殺者の森に巣くう怪物、アルピイエ。ダンテの『神曲・地獄篇』によるとその外貌は、「幅広の翼もち、頭と顔は人間なれど、足には鉤爪あり、ぼてぼての太鼓腹が一面羽毛で掩われ」ているという。自殺者たちは茨の木と化して、アルピイエに啄ばまれ、生木の痛みを味わい続ける。
時を浪費することは、自らを損なう行為であるという戒めであろうか。悪辣でも非道でもない、平凡なコモン君に下された審判としては、あまりに厳しいような気もするのだが…。

もう一つの鞄
公房には、もう一つ『鞄』という作品が存在するのをご存じだろうか。こちらは、『笑う月』に収録されている短編。
ここでの鞄は、所持品というより、持ち主の一部分であり、ナビゲーションでもある。しかし、どうやら上り坂が苦手らしい。赤ん坊なら、無理をすれば三つくらいは押し込めるというから、かなりの大きさだろう。行動が限定されることで、逆に解放感を手に入れるというパラドックス。男はいとも簡単に居場所を捨てて、「嫌になるほど自由」に歩み始めた…。
ちなみに『笑う月』は、公房の「創作ノート」という側面を持っている。例えば、『箱男』に貼付された写真の意図や、『ウェー(新どれい狩り)』に登場する人物のモデルについて触れており、発想の発芽からその生育過程まで、公房の意識下をなぞるようで実に興味深い。
また、もう一つの『密会』も収録されているので、読み比べてみるのも一興だろう。
公然の秘密
臭いものに蓋ではないが、これまで封印してきたものを突然目の前に突きつけられると、人間はやり場のない怒りを抱く。腐り落ちた鼻先を突き出し、腐りかけた足を引き摺って這い上がる仔象に、苛立つ見物人たち。古新聞のように仔象を焼き尽くしたものは、集団ヒステリーに他ならない。偽装やら粉飾やら、さまざまな問題が噴出している昨今。一部にとっては〝公然の秘密〟だったものが、爆発的に伝播しながら暴かれている。攻勢に転じたときの人間のエゴは、目を覆いたくなるほど醜悪だ。
高校の教科書にも採用された『公然の秘密』は、『笑う月』に収録。
自己犠牲
公房の作品群の中で、カニバリズム(食人)を扱ったものに、『事業』、『人肉食用反対陳情団と三人の紳士たち』、『自己犠牲』(『笑う月』収録)がある。
『自己犠牲』は、海で遭難した三人の生存者(コックと医者と航海士)の話。俺を喰ってくれと、互いに自薦し合うさまは滑稽で、『ひかりごけ』(武田泰淳)のパロディ版としても読むことができるだろう。「おらが死にたくねえわけはな。おら、おめえたちに喰われたくねえからだ」と、悲痛な叫びを上げた五助の心中とは、かなりの隔たりがある。なにしろ、喰べられることに崇高な(そして無上の)喜びを感じているのだ。喰べる側に回った者が、ハズレくじを引いたかのように本気で悔しがる逆転現象。無事救出された唯一の生存者は、皮肉にも遭難前より3キロ体重が増えていた…。
人魚伝
全身緑色の蠱惑的な人魚を、沈没船から連れ出した男。吸い込まれそうな潤んだ眼差しを愛撫し、緑色の涙を啜り、満ち足りた同棲生活となる筈だったのだが…。
食人を扱った作品群では出色の出来ばえ。ただ、風呂場が屠殺場と化す後半部分はかなりグロテスクで、心の準備が必要である。
文脈をたどるうちに、川上弘美の『離さない』(『神様』に収録)に酷似していることに気づいた。人魚、風呂場、端から端へなぞるような喰べ方と、この一致は川上弘美から公房へのオマージュと受け取って、差し支えないだろう。
彼女(人魚)を自主的に選んだつもりが、彼女に選ばれた家畜にすぎなかった主人公の述懐が哀れ。
公房にとって「緑」は特別な色であるらしい。それについてはいずれ、『緑色のストッキング』で言及したいと思う。

私小説を書かない理由
その1
作品は作者の属性ではない。だからみだりに、作品の周辺に、自分の素顔をのぞかせるべきではない。
その2
現在が、原型のままで過去に送り込まれることはなく、消化された現在は、たちまち過去一般に還元される。
その3
嘘を発明することのたのしさと困難さ。そのために小説を書く。どうせなら、ポーのように嘘をつくこと。
一寸後は闇。過去の作品を思い出すことなど、不快でしかなく、ペンよりむしろ、消しゴムを使って書きたい、という公房の本音がちらり。
エッセイ『一寸後は闇』より。
