
司馬遼太郎が描いた幕末・明治維新
最終更新日 平成18年(2006)6月21日



欧米に大きく立ち遅れた日本、形骸化した武士道、幕府の弱腰。封建制度の終末を早くから予見した河井継之助にとって、最終の目的は長岡藩を独立王国にすることであった。
長岡藩七万四千石の下級武士に生まれながら、広く諸国を遊歴した継之助はやがて筆頭家老(のちに総督)となり、長岡藩存続のために奔走する。官軍でも幕軍でもない、越後長岡軍であるとして最後まで中立を守ろうとするが、弱小藩の運命は、酸鼻を極めた北越戦争へと流転してゆく。
陽明学を学び、開明論者でもあった継之助は、あの狂気の時代にあって、柔軟さと冷静さを兼ね備えた賢人でもあった。もしも彼が天下国家の宰相であったなら、明治維新も大きく様変わりしたに違いない。惜しむべきは雪深い小国の産であったということ。彼を理解し、容れるだけの素地が周囲になかったと言えるだろう。
また彼には将軍の才もあり、長岡奪還の沼越え作戦について「緻密さ、堅牢さは、幕末維新および西南戦争にかけてのあらゆる戦争のなかでの最高の傑作」と司馬氏をして言わしめている。

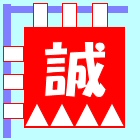

油小路の決闘
「私事で斬合いにおよんだとき、相手を斃さず自分のみが傷を負うた場合、未練なく切腹すべし」
新選組には恐るべき鉄の掟があった。 どうせ隊に戻っても死が待っているだけ。篠原泰之進が伊東甲子太郎と共に隊を離脱した理由はそこにあった。「耳洗い」の奇癖を持つ男を薬味に添えて、伊東甲子太郎暗殺前夜を描く。
美しく散ることを選ぶか、生き長らえることを良しとするか、男の美学を問う佳品。
芹沢鴨の暗殺
酒、女、金。乱行の餓虎と化した芹沢鴨を誅殺するまでを描く。
この章では、心やさしいのか冷血なのか、得体の知れぬ沖田総司の、「燃えよ剣」ではあまり語られなかった人間像にも迫り興味深い。 「可哀そうだな」と呟きながら、芹沢を斬るのは自分だと主張し、みごと鮮やかな一閃で一の太刀を決める。
長州の間者
長州の間者は自分の他にもう一人いる。隊士たちの挙動、顔色を窺って、そのもう一人をさぐる深町新作。 深町が斬られる描写は一切なく、「深町の死骸の横で沖田総司が、鉾を無邪気にながめながら丹念に刀をぬぐった」と締めくくる。総司の、あっけらかんとした鋭さを垣間見るような一コマ。
池田屋異聞
赤穂事件の義士と裏切り者。その世評は百年を経た幕末の頃にも色濃く残っていた。
裏切り者の曾孫、山崎蒸が、薬売りに変装して内側から池田屋襲撃の手引きをするが…。
鴨川銭取橋
軍学、兵法に秀でていた武田観柳斎。才子肌の人間を好まない土方によって、武田は内通者に仕立て上げられ、お膳立て通り隊を裏切ってしまう。
人間の行動を先読みする土方からすれば、武田の裏切りは近い将来必ず起こりうることであった。隊が深手を負わないよう、未必の裏切りを処罰したと言えるであろう。
虎徹
思い込みは度が過ぎると信仰となる。業物ではあるが、「虎徹」とは似ても似つかぬ差料を、「虎徹」として崇め慈しむ近藤勇の姿が滑稽味を誘う。
前髪の惣三郎
映画「御法度」でお馴染みのストーリー。男ばかりの集団においては、時としてとんでもない衆道の化け物が出現する。
胡沙笛を吹く武士
妻帯し子をもうけると男はたちまち怯懦になる。命惜しみするような輩は新選組に必要なく、「士道不覚悟」の断罪が待ち受けるのみ。
三条磧乱刀
これも映画「御法度」に挿入された逸話。同門の先輩、井上源三郎を守ろうとする近藤、土方、沖田らの慌てぶりが微笑ましい。
海仙寺党異聞
灯台下暗し、敵は身近なところに潜んでいた。会計方の長坂小十郎が、平素からは想像もできないほどの胆力をみせる。
沖田総司の恋
「あんないい娘が、私になんぞ、好いてくれるものですか」
痛々しいまでの総司の純情。滝の清しさも、総司の一途さを前にかすんでしまうほどだ。恋の仲立ちにはいたって不向きな、近藤、土方のご両人。濃やかな情を理解できない武骨な一面が可笑しくもある。
槍は宝蔵院流
近藤に取り入り、「倅」を養子として差し出した谷三十郎。しかし、その養子周平が池田屋事件で大失態を演じ、谷の人気は俄かに衰えてゆく。ツキから見放された男の行く手に、恐るべき殺人剣の使い手、斎藤一の一閃が待ち受けていた。
弥兵衛奮迅
薩摩藩の富山弥兵衛こそ天稟の間者であった。人の良さそうな顔でみごと新選組を欺き通す。
四斤山砲
永倉新八の師匠と名乗る男がある日、おそれ気もなく屯営の門を叩く。器用に立ち回って砲術師範頭という地位を勝ち取るが、新選組は素人同然の屑を拾って、それまで砲術方であった阿部十郎を薩摩藩に走らせてしまう。
菊一文字
細身で腰反りが高く、刃文は一文字丁子と呼ばれる広い焼幅。乱れが八重桜の花びらを置き並べて露をふくませたように美しい。菊一文字という、稀代の名刀を借り受けた総司であったが、血で汚すことを嫌い、目の前の敵から逃げ出してしまう。
「生まれたままの男」と土方に称された総司の、きらりとした人物像は、菊一文字にも似かよう美しさと言えるだろう。

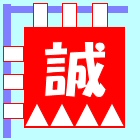

自分より分際の高い女を好み、宮司猿渡家へ忍び込んだがために人を殺めてしまったバラガキ(不良少年)、土方歳三。それが元で甲源一刀流の使い手、七里研之助に命を狙われることとなるが…。
バラガキ時代の圧巻はなんと言っても分倍(ぶばい)河原の決闘。総勢二十人を敵に回し、沖田総司と二人で斬り込んでゆく姿は、新選組副長と一番隊長のそれを彷彿とさせる。歳三の緻密なまでの計画性は、この時すでに、非凡な軍略家としての片鱗を覗かせていて興味深い。また、返り血も浴びない総司の太刀筋は、身も凍るような美しさと呼ぶより他ないであろう。
惚れぼれ語録…「無茶だよ、土方さんの軍略は。さっき賞めて損しちゃった」上巻P73(総司)
将軍警護という名目で招集された浪士組であったが、清河八郎は天朝を奉じてそれを尊皇攘夷の先駈けにしようと目論んでいた。
あからさまな反幕運動に出た清河に対し歳三は、芹沢一派を抱き込んで新党結成のために動き出す。勇猛だけではない歳三の資質は隠しようもなく、野性的な嗅覚と観察眼によって、組織を束ねていく才は天賦のものと言っていいだろう。山南敬助を副長から総長に格上げし、巧みに組織のラインから外すなど、現代のサラリーマン社会にも通じる独特の経営学が、随所で遺憾なく発揮されている。
三百年、怠惰と狎れあいの生活を世襲してきた幕臣や諸藩の藩士とは違い、「武士」という語感に初々しさを持っている近藤、歳三の鮮烈な美学(上巻P242)。荒淫にただれた芹沢一派とはまさに好対照と言えるだろう。
惚れぼれ語録…「私は近藤先生と土方さんの往くところなら地獄でも行きますよ」上巻P151(総司)「しかしそのときは私の、土方歳三の生涯もおわる。あんたの死体のそばで腹を切って死ぬ。総司も死ぬだろう。天然理心流も新選組も、そのときが最後になる」上巻P229(歳三)
長州の吉田稔麿、肥後の宮部鼎蔵など、第一級の志士たちが斬殺された池田屋事変。ここで司馬氏は興味深い私見を述べている。「池田屋ノ変によって明治維新が少なくとも一年は遅れたと言われるが、おそらく逆であろう」(上巻P313)つまり、長州を筆頭とする倒幕の軍事行動が、これによって一気に加速したと観るべきで、新選組は言わば火付け役を演じたと言えなくもない。確かに明治政府を担ったであろう貴重な人材を失ったが、この事件が新しい時代への原動力となったことは想像に難くなく、なんとも皮肉な結末である。
周旋(政治)好きの近藤からすれば、政治に無関心な歳三は今ひとつ物足りない。北辰一刀流の剣術指南であり、水戸学の思想家でもある伊東甲子太郎を、近藤は喜々として新選組に迎え入れるが、伊東には、いずれ新選組を倒幕の義軍にしようという肚があった。御しやすい近藤より土方を恐れた伊東は、因縁の七里研之助にこれを討たせようと謀る。
惚れぼれ語録…「おれァ、職人だよ。志士でもなく、なんでもない。天下の事も考えねえようにしている。新選組を天下第一の喧嘩屋に育てたいだけのことだ。おれは、自分の分を知っている」上巻P369(歳三)「君は、ふしぎな若者だなあ。私は君と話していると、神様とか諸天とかがこの世にさしむけた童子のような気がしてならない」上巻P381(山南敬助)「副長が、山南や伊東みたいにいい子になりたがると、にがい命令は近藤の口から出る。自然憎しみや毀誉褒貶は近藤へゆく」上巻P383(歳三)
銃弾に倒れた近藤と、病状が重くなる一方の総司と別れて、孤軍奮闘する歳三。が、意気消沈するどころか、「おれの真の人生は、この戦場からだ」と、いよいよ喧嘩師の血がたぎるさまは、いかにも“バラガキのトシ”らしい。
鳥羽伏見の戦いは、幕軍にとっては負けるはずのない戦さであった。しかし、「官軍」という名前と時流が、兵力の少ない薩長土に味方し、将軍慶喜の徹底恭順もあって、幕軍は総崩れのていで退いてゆく。「日本の歴史は関ヶ原でまがり、さらに鳥羽伏見の戦いでまがった」とする司馬史観であるが、両戦の悲劇的共通要素についても、歳三の口を借りて触れている。「わるい卦だよ」という危惧と予感、それがひとつずつ的中してゆく過程と、北征への道のりが重なり、物語は終章へとなだれ込む。
西昭庵でお雪と夕日を眺める場面。落日を華やかと観たところに、歳三流の美学があるようだ。紅(くれない)に染まりながら消えゆく風情に、潔い美を感じるのだろう。「毎朝毎夕、改めては死に改めては死に、常住死身になりて居る」という葉隠れの精神にも通じ、興味深いくだりである。今日ひとひを、二度と巡り逢わない一期一会のものと覚悟して生きる後ろ姿に、哀感が漂う。
惚れぼれ語録…「どうなる、とは漢(おとこ)の思案ではない。おとことは、どうする、ということ以外に思案はないぞ」下巻P75(歳三)「たとえ幕軍がぜんぶ敗れ、降伏して、最後の一人になろうとも、やるぜ」下巻P76(歳三)「男の一生というものは、美しさを作るためのものだ、自分の」下巻P77(歳三)「尊氏かなんだか知らねえが、人間、万世に照らして変わらねえものがあるはずだよ。その変わらねえ大事なものをめざして男は生きてゆくもんだ」下巻P166(歳三)
疲れ、枯れ切った魂は、ただ死に場所を求めてさまよい、鬼神のごとき闘争本能に曳かれるまま、北の果てへとたどり着く。変節も怯懦も無縁なこの男の生涯は、完全に燃え尽きたと言っていいだろう。五稜郭陣営がこぞって降伏の姿勢をとるなか、生き延びることを潔しとしない歳三はひとり騎上の人となり、悠然と官軍参謀府へ向かう…。
惚れぼれ語録…「その過去の国には、お雪さんも近藤も沖田も住んでいる」下巻P394(歳三)「やったよ、お雪」下巻P400(歳三)「新選組副長土方歳三」下巻P431(函館政府の陸軍奉行とは名乗らず、最後はあえて悪名高きこの名を告げる)

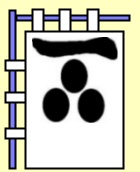
その生涯で二十一回の猛を発しようと誓った松陰だったが、結局三回発したのみで二十九年という短い生涯を閉じ、残りの十八回は松下村塾の若い門人達に託すかたちとなった。さて、その三回の猛とはいかなるものであったのだろうか。
第一の猛…脱藩
たかが友人との約束を守るために藩命に背き、ついに脱藩した松陰吉田寅次郎。しかもこの時期は、脱藩が流行した幕末期ではなく、幕藩体制の秩序美が保たれている頃であった。玉木文之進によって、粉骨砕身、公につくすべき人間として教育された寅次郎が、なぜ公より私情を優先させたのか。寅次郎にすれば、
それは「人間の本義のため」であり、人間の本義とは約束を守ることであって、破れば長州武士の名折れ、ひいては藩に対する罪となるというのである。なんとも理屈っぽい話であるが、純粋思考の彼にとっては、友人との約束も、プライベートとして割り切れるものではないということなのだろう。
※友人とは肥後の宮部鼎蔵と南部の江幡五郎。約束とは東北旅行のことで、会津、新潟、米沢、秋田、青森などを歴訪した。
第二の猛…「将及私語」
ペリーが浦賀に来航し、日本中が驚天動地の騒ぎとなった嘉永六年、師の佐久間象山とともにその威容を目の当たりにした寅次郎は、とんでもない行動に出る。なんと時の藩主、毛利慶親に「将及私語」と題した意見書を上申したのである。その内容は、外国と対等に渡り合うための、藩政改革についてであった。藩組織の独裁体制を確立すること、藩外の賢人を招き藩主の側に置くこと、銃砲はすべて西洋式にし、西洋軍艦を買い入れること云々と続いている。礼を欠き、序列を無視した直訴は、当然咎められるべき行為であったが、さしたる処罰を受けなかったことは驚きである。若者に甘い長州藩の体質なのか、それとも寅次郎という人間が人に愛される性質なのか。興味深い挿話である。
第三の猛…密航
攘夷運動の複雑さは、洋夷の文化を輸入しなければ、けして洋夷には勝てないということである。つまり、これまで通り鎖国を貫くならば、中国の二の舞になることは必定であり、便宜的に一時開国するか、密航して敵情視察でもしなければ、攘夷運動の活路は見出せないのである。意外にもこの真理にいち早く気づいたのは、攘夷運動の祖とも言える松陰自身であった。しかし、広い世界を見聞したいという彼の悲願は破れ、国家の大禁を犯した重罪人として、門人の金子重之助とともに縛に繋がる結果となった。「どう反省しても非難されるべきことは何ひとつない」と、檻のなかで述懐する心中には一点の曇りもなく、ここまでくれば凄まじいばかりの「狂」というよりほかない。
教育者としての吉田松陰
松陰の教育法は、門生の長所を的確に引き出しておだて、発奮させることである。どんなひねくれものでも操縦するツボを心得ていて、まさに天職と呼ぶにふさわしい教育者であった。現代の学校教育は、「個」というスローガンを掲げながら、結局は平均化の教育から脱しきれないのが実状である。松下村塾においては、擢んでているところを十二分に伸ばす、文字通り「個」に応じた教育が実践されていたことは想像に難くない。高杉晋作、久坂玄瑞を筆頭とする、多くの人材を輩出した所以であろう。また、松陰はあくまで「教師無報酬」主義を貫き、百姓罪人問わず広く門戸を開いた。教師というより同輩、「いっしょに学びましょう」という姿勢で接したと伝えられている。
「人間の人生(いのち)とは不思議である。たとえ少年の身で死んでもその短さのなかにちゃんと春夏秋冬がある」と、かつて松陰は言った。松陰がもっとも愛した門弟高杉晋作の、その二十七年八ヵ月の生涯を、春夏秋冬で辿ってみようと思う。
春 塾生時代
いわゆる上士と呼ばれる家系の跡取息子として、この世に生を受けた高杉晋作。彼は一人息子である上に生まれつき呼吸器が弱く、甘やかされて育ったお坊ちゃんであった。そのせいか目上の人間に対しても大胆なふるまいが多く、負けん気の強い子どもであったらしい。松陰はそういう晋作の気質を見抜き、わざと久坂玄瑞と比較して「久坂君のほうが優れています」などと言って、競争心を煽るようなまねをした。また、久坂には「狂」を奨めながら、晋作には「十年間は静かにしていろ」と、ブレーキをかけるような助言をしたのは、ともすれば暴走しがちな晋作のはねっかえりに、危機感を覚えたのかもしれない。
夏 疾風怒涛
この男にとっての転機は、やはり上海への洋行である。西洋文明に触れた者の多くが開国主義に転じるのに対し、晋作はさらに攘夷思想を強くした。また、国の外から見れば、幕府は大名の最大のものにすぎず、二、三の藩が決起すれば、それに取って代わることができると確信したのである。この時点で、革命こそが彼の生涯の目標になったと言えるだろう。
そして帰国後最初のはねっかえりが、「御殿山焼打ち事件」である。御殿山には、当時建設中の英国公使館があり、そこを攻撃すれば対外的な示威行動になると同時に、幕府の面目をつぶすという、一石二鳥の効果があった。その辺の機微を捉える直観力は天性のもので、尋常ではない。
江戸ではその他にも、松陰の遺骨を盗み出して改葬した「御成橋事件」、将軍家茂暗殺計画(未遂に終わった)など、立て続けに「狂」を発した晋作であるが、突如萩に帰り「十年身を慎む」などと口走っている。これがまた晋作という若者の可笑しさで、頭を丸めて出家し、東行と名乗る念の入れよう。しかしそれも長くは続かなかった。あろうことか、長州が藩をあげて攘夷狂いしたのである。長州藩の攘夷とは、関門海峡を通過する外国艦船を、下関沿岸の砲台から攻撃して、打ち沈めることであった。外国と幕府を一挙に敵に回した長州の、新しい戦力を必要とした背景がここにあり、晋作を総督とする奇兵隊の誕生へと繋がってゆく。が、来島又兵衛らの暴走を食い止めるため、結成して間もない奇兵隊を放り出して脱藩、単身京へ向かった晋作。攘夷党でも俗論党でもない、三人党(晋作・井上聞多・伊藤俊輔)の孤独な戦いがこれより始まる。
※井上聞多…のちの井上馨。イギリス留学により開明論者に転向。稀代の癇癪持ちであったが、歯に衣着せぬ言動は藩侯に愛された。維新後、尾去沢銅山事件を起こして司法卿江藤新平に糾弾された。
※伊藤俊輔…のちの伊藤博文。井上とともにイギリスへ留学。晋作の使いっぱしり的役割を担う。日本最初の総理大臣。
秋 革命児、高杉晋作
思うがまま攘夷運動を展開してきた長州であったが、その大反動が藩を襲う。四ヵ国艦隊が、大挙して下関に押し寄せてきたのである。窮地に立たされた藩は、和睦交渉役として晋作を抜擢するが…。
敗者の代表でありながら、晋作のふてぶてしい魔王ぶりにイギリス側は圧倒される。賠償金についても「攘夷は幕府の命令で仕方なくやったこと」と、幕府に肩代わりさせるところなど、千両役者と言うよりほかない。しかしこれにより、「洋夷に降伏するとは売国行為である」と、藩内の過激分子に命を狙われることとなり、晋作は逃避行の旅に出る。が、事態はまたもや急展開。藩上層の攘夷派が一掃され、佐幕派がこれに取って代わったのである。晋作は、クーデター部隊を率いて下関(馬関)を占領、萩の佐幕派と対峙した。領民を巻き込んだ内乱は、晋作ら革命軍の勝利に終わったが、安堵の息もつがせず、今度は幕府の長州征伐が待ち受けていた。
冬 馬関に果つ
大島に上陸した幕軍を、奇襲作戦で破った晋作。だが彼の身体は病魔に冒され、維新を待たずして帰らぬ人となった。
もし晋作が革命期ではなく、別の時代に生まれていたなら、あるいは詩人になっていたかもしれない、というのが司馬氏の見方である。とは言っても、万事派手好きの彼のことだから、おとなしく詩を書くだけでは満足しない、かなりの放蕩人生となったことだろう。思想が即行動に直結する、松陰譲りの激しさがあり、まさに「動けば雷電の如く発すれば風雨の如し」(伊藤博文による撰文)の行動力の持ち主であった。
自己犠牲的革命論
晋作が描いていた革命は、大義のためなら進んで捨石になろうという、自己犠牲的なものであった。
「長州がその藩地である防長二州に籠もり、独立した軍事国家になり、幕府と決戦し、木っ端微塵に敗けてしまう。しかしその大戦さの経過中に三百諸藩は大混乱をおこし、右往左往し、あるいは幕府につき、あるいは長州につき、乱世になり、めったやたらと混乱するうちに長州もほろぶかわりに幕府もほろび、それによって自然のいきおいであたらしい秩序がどろどろと地中からせりあがり、湧きあがって、いままでにない日本をつくりあげる。その日本こそ、列強の侵略に堪えうる日本である」(三巻P51~P52)
事実歴史はそのようになった。ただ違うのは、長州は滅びず、明治政府(薩長体制)の基礎を作り上げたということである。維新まで生き残った連中は政治家になった。体質的に政治家になれなかった晋作は、革命家としての使命を全うしたと言っていいだろう。

出処の卑しさのために、母藩である長州において、その存在すら認知されていなかった村田蔵六(大村益次郎)。
幕末のぎりぎりになって登場した天才戦術家は、緒方洪庵によって見出され、伊予宇和島藩の御雇となる。この逸材を他藩に持ってゆかれ、なんとか長州の軍師に据えたい桂小五郎であったが、身分というものに頑迷な藩政が、容易にそれを許さない。医術を体得し、語学にも堪能な益次郎の真骨頂は、計算し尽くされた軍略にあった。諸葛孔明さながら団扇片手の身軽さで、幕軍を蹴散らし、彰義隊をも壊滅した彼の、一切の無駄を省いた挙動は、時に不遜と映り、人の反感を招いた。幕末を生き抜き、維新を見届けた益次郎であったが、最期は薩摩藩士等の兇刃に倒れることとなる。(明治二年没)
大小の抜き方も知らない、馬にも乗れない。しかしそんなことはまったく意に介さない、強烈な自負が益次郎を支えていた。この方程式通りに実行すれば、必ずや事は成功するという確信。あの時代にあっては希少価値とも言える、科学的思考回路の持ち主であった。

無学、無思想、殺人嗜好者。極めて遺憾ではあるが、岡田以蔵を絢爛たる志士群の列に加えることはできない。が、敢えて、彼の血塗られた足跡を濯ぐべく、ここに付記する。
万事折り目正しい武市半平太の目には、常に以蔵への侮蔑が浮かんでいた。武市は以蔵を番犬として扱い、同志として扱うことがなかった。他藩の志士と議論する時も輪の埒外に以蔵を置き、必要な時だけこれを利用した。人を斬ることが、唯一の存在理由(アイデンティティー)となったのも無理からぬことである。竹刀舞踊ではない殺人剣の凄まじさ、以蔵の太刀筋をもっとも怖れていたのは、他ならぬ武市ではなかったのか。師でありながら、弟子(以蔵)を慈しむことのなかった狭量が、残念でならない。西郷隆盛の子飼いだった〝人斬り半次郎〟こと中村半次郎(のちの桐野利秋)と明暗を分けたのは、ひとえに飼い主の度量の差であったと言えるだろう。文字通り宿無しとなった末路は、あまりにも惨めだ。
