戻る
つぎの「生い立ち2.」へ


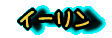
坂を登りきった丘の上に白い小さな家があった。同じ造りの住宅群の入り口が私の家だった。西向きの玄関があって、白い漆喰の壁が輝くように西日を反射している。いつも眩しく見えた。
「あれっ、道をまちがえたのかな。」
晩秋の午後ランドセルを背負って坂を登って来た私は、一瞬とまどった。いつもの白い家が真っ赤に見える。近づいてよく見ると、壁には隙間なく赤いテントウムシが止まっていた。大小さまざまのテントウムシがひしめき合っていたのである。テントウムシでできた壁のようだった。小学校1年生の秋の鮮やかな記憶だ。
私はこのこ ろから断片的に記憶が残っているようになった。それ以前の記憶は瞬間の記憶としての残っているものもあるが大体が親から聞いて作られた思い出ではないかと思う。テントウムシの日向ぼっこは一日だけだった。テントウムシに限らず、生き物にはある時一斉に集まることがあるようだ。鉄条網にスズメが真っ黒に群れていたことがある。父のあとをついて、鉄砲打ちに行った。散弾銃で撃ったスズメを拾わされた。いくらでも獲れて、拾って麻の袋に入れるのだが、小学校1年生に持てるのはたかが知れている。
毎晩、やかましく虫が鳴いた。蚊帳を吊って中で、その虫の声に囲まれて眠る。ある晩、特別大きな鳴き声が、すぐ近くで聞こえた。見つけようとしても姿は見えず、諦めて寝床に入るとまた鳴き出すということが続いた。三日も四日もそれが続いた。数日後、朝、大きなキリギリスが蚊帳にくっついて潰れていた。私は、母が潰したと猛烈にくってかかった。誰もいないところに行って墓を作って大泣きした。童話のような話だがはっきり覚えている。
これらの話は、中国東北部、昔、満州国牡丹江省イ−リンという村に住んでいた時のことだ。村と言えるかどうか分からない。軍の宿舎が並んでいた所だ。山砲隊が駐屯していた。一晩だけだったが、ゲリラが襲ってきて銃撃戦になった。夜中だったが布団を被っていろと言われて、部屋の隅に縮まっていたことを覚えている。大人たちが次の日大砲があるのにどうして使わなかったのだろうと話していた。大人は匪賊が出るという言葉を使っていたが、治安は必ずしも良くなかった。
イ−リンに学校はない。私は、他の軍人軍属の子どもたち数人とともに近くのム−リンという街の学校に通った。通学用の列車は、先頭の機関車に最後部の車掌の車をつないで、途中の車両は全部省略ということが多く、私たちの通学のために仕立ててくれた列車であろう。小さな機関車がのろのろと走る。私は最後部で足をたらすと1年生の足でも地面に着くようなものだった。つま先に枕木がリズミカルに当たるのが楽しかった。
これをやるとさすがに上級生に襟首を捕まれて車掌の部屋に引きずり戻された。すきを見てまた這い出していくのも楽しかった。
学校の門の丸太にはム−リン日本人尋常高等小学校と書いた木札が打ち付けてあった。全校で60人の子どもがいた。校庭と呼べるのかどうか、木に囲まれた広場で全校入り乱れて鬼ごっこをした。二手に分かれて敵、味方、それぞれが、戦艦、駆逐艦、潜水艦に分かれる。戦艦は潜水艦に負ける。潜水艦は駆逐艦に負ける。駆逐艦は戦艦に負けると言う「じゃんけん」と同じ仕組みで追い掛け合う。小学校の低学年でも高等科の大きな生徒の油断をみて勝てるのでとても楽しかった。この学校では何を習ったのだろう。そのことしか覚えていない。
坂道を登って家に帰る途中、キジが蹲っているのを知らずに踏みつけそうになり、羽音に肝を冷やしたこともあった。何者であったか、蛇の心臓を動いたまま飲むやつがいた。
家に猟犬が2頭おり。茶色の方は毛が長くおっとりして、目が良く見えないと聞いていた。父の言うことしか聞かず、母が邪魔になるからどけと言っても絶対動かない。「お父さん何とかして。」というと父が、奥で顔も見せずに「ミッチ−どけ!」と言うだけですごすごと外に出ていくという犬だった。昼は父の仕事場のデスクの下から動かないそうだ。列車でとなり街に行って宴会をしている時、列車を追いかけてきたのであろうか、宴会の座敷に飛び込んできたことがあると父が喜んでいた。
白に黒のぶちのあるセッタ−はベッグという名で対照的なバカ犬だった。私の遊び相手にはいいが、一つ悪い癖があって、鎖を離すと、糞まみれになって帰ってくる。その汚いことたるやである。父は鉄橋まで連れて行ってかなり高い鉄橋の真ん中から、川に蹴落とす。もんどり打って落ちていくが、岸にたどり着く頃はきれいになる。一度などは、家に着くまでまた糞の上を転がってきてしまったことがあった。
ここ、シベリヤに近い満州で長く暮らしたら、私も野生人のように育ったに違いない。ここにいる間に、二人目の妹が生まれた。「かおる」という。
前のペ−ジに戻る 次のペ−ジに進む トップに戻る