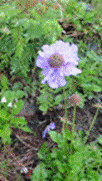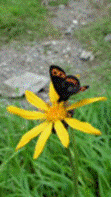|
南アルプス(千枚岳~悪沢岳[荒川三山]~赤石岳~大沢岳~兎岳~聖岳)を縦走しました (H29.8.1~5) |
||||||||||||||
|
平成29年7月31日(月)~8月1日(火) 2年越しの計画がやっと叶った。当初は4日間で縦走の予定だったが天候や体力の衰え・安全を考えて一般的な5日間で歩くことにした。それにしても登山口の椹島に入るまでが長い。でも旅好きな私としては新幹線や6時間も乗ることになるバスの長旅でも、それは楽しみとなるものだった。 東京から西に向かう新幹線に乗ったのは20年ぶりぐらいだろうか。曇天で富士山は見えなかったが1時間の車窓から流れる景色をどん欲に楽しんだ。降りた静岡の駅は暑く、登山口の草薙ダムに向かうバスの発車時刻まで駅ビルの中で涼む。予約制のバスは8割がた登山者で埋まった。さすがに静岡はお茶の産地で、山間の斜面は茶畑が目立ち、大規模なものや庭先の小さい茶畑もある。いずれも真っすぐ蒲鉾型に刈られていて緑の綺麗な景色を見せている。ガイドさん(乗降確認の係りの人)が静岡市には3区あり、駿河区、清水区、葵区であるが、南アルプスに向かうここ葵区はバスで3時間走っても葵区から抜け出せない、それほど広いと笑っていた。どんどん山奥に進みバスは途中2ヶ所でトイレ休憩。峠を二つ越え井川の集落へ。山深い井川は大変美味しい高原野菜の産地でもある‥‥との話なので、休憩の井川駅前の露店でトウモロコシとトマトを買いバスの中で食べる‥‥確かに美味い。林業で栄えた井川の集落は、いまは高原野菜と峡谷の中を走るアプト式列車やダム湖の井川湖の観光地でもある。 着いた畑薙ダムの臨時駐車場から、椹島に向かう東海フォレストの登山者送迎バス(椹島ロッジなどの宿泊者のみ)に乗り替える。満員状態のマイクロバスは大井川の峡谷に沿った未舗装の細い道をさらに山深く走っていく。一般車両の通行は禁じられているが、工事の大型トラックと何度もすれ違い渓谷に落ちないかハラハラする。ときどき悪路で車の底が地面に接してドカンという衝撃が凄い。とにかく山深いしⅤ字峡谷の底を這う感じで走り、やっと椹島に着いた時にはホッとした。 椹島・東海フォレスト事務所は山小屋ではなく、元々森林管理や伐採を仕事とする社員の宿舎だったようで、風呂もあるし部屋も食事も旅館という感じだった。部屋数は多いが割り当てられた部屋は狭く、ここに6人が入ると眠れそうにない。受付でさらに2,000円追加すると個室に泊れると聞いていたので、明日から3泊することになる山小屋でも眠れないことを思い個室に移動することにした。 21:40八戸~(高速バス)~7:15東京駅8:03~(新幹線)~9:05静岡駅9:50~(しずてつジャストライン・3,100円・要予約)~13:15畑薙臨時駐車場14:30~(東海フォレスト・ロッジ宿泊者無料)~15:30椹島ロッジ(泊) |
||||||||||||||
|
草薙ダム臨時駐車場 ここで東海フォレストバスに乗り換える |
椹島・東海フォレスト事務所 |
個室にはテレビも付いている |
||||||||||||
|
平成29年8月2日(水) 椹島からの登山コースは千枚岳から悪沢岳へ向かうコースか、赤石岳へ真っすぐ登るコースがある。百名山(悪沢岳・赤石岳・聖岳・光岳)の縦走を目的とする登山者が多いが、そうなると数日間は同じ顔ぶれの人と同じ道を歩くことになる。今回も東京練馬区の若い人、光岳まで縦走する広島生口島の人、岐阜の県庁退職者の三人とは縦走路中を前後しながら同じ山小屋で話し込むことになった。 椹島は標高1,120㍍でありこの日の目的の千枚小屋は2,565㍍。予定では小屋には12:30に到着し、時間があるので千枚岳を往復し明日歩く縦走路を展望するつもりであった。 ロッジを出発する時は青空が広がり絶好の登山日和のはずだった。ゆるやかな登りがひたすら続き、展望のない樹林帯を喘ぎながら登る。途中の見晴らしの利く尾根からは悪沢岳も綺麗に見えていた。しかし標高が高くなるにつれて徐々に雲が架かりだし、やがて霧雨状態になってしまった。途中の清水平で水を補給する。「平」の文字が付くものの樹林の斜面の水場だった。期待していた見晴岩に立つと目の前は白くガスって全く展望なし。晴れていれば赤石岳や荒川三山が大きく目の前に広がるはずだった。標高は2,000㍍を越え登山道は樹齢200年を超えるダケカンバやシラビソの混交林となり、「暗い森だが夏は日光を遮り皆様の汗を少し減らしてくれる優しい森です」‥‥と東海フォレストの案内板に書いてあった。風はなく蒸し暑く汗と霧雨でびしょ濡れで、駒鳥池からはとうとう雨となって雨具を着こんだ‥‥こんなはずではなかった (^_^;)。 予定より1時間も早い11:30千枚小屋に到着。宿泊手続きは12:30からと言われ霧が流れる小屋前のベンチで、椹島ロッジで作ってもらった弁当を食べる。この弁当殻は最終日の白樺温泉までザックの中で同行となった。後から着いた練馬の兄さんとしばし話す。地図を眺めていたら「もしかして荒川小屋まで行くつもりですか?」と考えを読まれてしまった。そう‥‥時間的には荒川小屋まで歩ける(予約は必要ないし)のだ。が、展望も無い険しい岩場を歩いても楽しい訳がない。千枚岳でも往復したいがそれも雨では‥‥と諦めた、明日の天気に期待しよう。 受付を早めに済ませると壁際に寝場所を取れるのだが、わずかに遅く後から着いた広島の人に壁際を取られてしまった。寝具はシュラフ。いままで何度も山小屋に世話になったがシュラフは初めてで、この後の二つの小屋も同じであった。雨の中、次々に濡れた登山者が到着し湿気の山小屋は満杯状態になってしまった。やはりイビキが酷く、十分に眠ることができなかった。暗闇の小屋の外は雨が降り続き、遠く雷鳴も聞こえていた。 椹島5:50~6:50鉄塔横~8:40清水平~9:40見晴岩~10:45駒鳥池~11:30千枚小屋~12:30宿泊受付(泊) |
||||||||||||||
|
椹島ロッジから登山口へ |
千枚岳への登山口で |
悪沢岳が見えている 晴れ間はここまで、これ以降二日間は全く山々は見えなかった |
||||||||||||
|
霧雨の千枚小屋 |
満員状態の寝場所 |
夕食 |
||||||||||||
|
平成29年8月3日(木) 朝、寝場所が隣の広島の方がスマホで今日の天候を調べていた。山域ごとに詳しい天気が分かるらしく、悪沢岳周辺は晴天で終日絶好の登山日和となっていた。ところが外は霧雨。互いに変だなと首を傾げた。今日は悪沢岳と赤石岳の3,000㍍の峰を超えて百閒洞山の家まで歩く。長い間憧れていた南アルプスの雄大な景色を楽しめるコースなのだ。ロングコースでもあり、早立ちしたいので朝食4:20は有難かった。ところでどこの小屋のご飯も美味しく、朝晩とも山盛りで二杯も食べてしまった。 雨具を着るほどでもなく、いきなりの急坂を千枚岳を目指して歩き出す。霧雨の千枚岳(2,880㍍)から花々が見えだした。タカネマツムシソウやタカネビランジは初めての花だろう。霧雨の中でデジカメのシャッターを押すのだがそれだけで安心して、あとで休憩の時に確認したらぼやけていた。霧雨でレンズが曇ったようだ。改めて花を見つけようとしても千枚岳を過ぎると再び見つけることができなかった。展望は全くなく、積み重なった巨岩を慎重に登り降りする連続。やがて3,000㍍の縦走路となり丸山(3,032㍍)を越え、いつの間にか悪沢岳(荒川東岳3,141㍍)の頂上に。今も思い出そうとしてもどんな山なのか登山道だったのかも思い出せず、全くつまらない3,000㍍峰となった。悪沢岳からの下りは特に注意が必要で長い梯子も架かっているところもある。とうとう雨が降り出してきて急いで雨具を着こむが風が無いのが幸いであった。中岳避難小屋は素通りして中岳(3,083㍍)の標識を横目に過ぎ、縦走路からは外れるが前岳(3,068㍍)に向かう。荒川三山に登ったと言うためには前岳を外すわけにはいかない。往復15分くらいで再び縦走路に戻ってきた。前岳の斜面をトラバースぎみに下ると広々としたお花畑になった。ニホンジカの食害を防ぐために大規模に柵が作られていて、登山道は入口の扉を開けて下っていく。素晴らしいお花畑が広がり、いきなりクロユリを見つけて驚いてしまった。ハクサンイチゲの白とミヤマキンバイの黄色が斜面を飾っている。山岳雑誌ではお花畑の背後に赤石岳が聳えているのだが、全くの雨と霧雨の繰り返しの中では気分が下降気味になる。たぶん二度とこのコースは歩くことはないだろう、他にも行きたい山はたくさんあるのだ。荒川小屋では雨が上がり少し空が明るくなり雨具を脱ぐ。水場で水を補給すると草の中に荒川小屋の朝食券を見つけた。小屋に届けると何が可笑しいのか女性従業員が数人で笑っていた。 大聖寺平からまたまた雨が降り出し、展望も無く急登となった岩場の道を喘ぎながら黙々と登る。小赤石岳(3,081㍍)の山頂近くで雷鳥の親子を見つける。親鳥は岩の上で遠くを見ていて、雛はその近くで歩き回っている。人には全く興味はないようでデジカメを向けても全く動かない。辛い登りを一瞬にして忘れさせてくれた。赤石岳(3,120㍍)山頂で写真撮りを頼まれる。それではと互いに写真を撮りあうが、霧の中で山頂の標識と一緒の写真では全く面白くないものだ。ただ標識の「赤石岳」の文字が赤いのが可笑しかった。少し下った赤石岳避難小屋のベンチで昼食。予定より2時間早く、千枚小屋で作ってもらったおにぎり(野沢菜、ヒジキ、梅干し)を食べる。のんびりしていると練馬の兄ちゃんが着いて、小屋にあったカップラーメン・ドンベーを注文していた。小屋の親爺は「ドンベーの注文は久しぶりだな~‥‥」と言っていた。賞味期限は大丈夫なのか、値段はいくらなのか、興味があったが寒くなってきてこちらは間もなく下山。馬の背のなだらかな稜線をどんどん下っていく。すると霧の中に赤石岳がぼんやりと見えだした。広々とした百閒平に着くと青空が見えだし雨具を脱ぐ。さらに下っていくと、アー~スゴイ‥‥百閒洞山の家に下る深い峡谷の向うに緑の山々が霧の中に見えだした。急いで地図を広げるとその山々は小兎岳、中盛丸山、大沢岳の連なりであった。急ではあるが山の家から登る登山道もはっきりと見え、やっと願っていた本来の山の景色となった。天候は好転する兆しであった。 百閒洞山の家は定員60名の小さな山小屋。受付を済ませ濡れた衣類や雨具をベンチに広げる。山小屋はコンパクトな作りだが入口・寝場所・食堂・洗面所・トイレ(水洗)への動線が短く、しかも綺麗な山小屋であった。ただ小屋全体に常に「ズンチャカ・ズンチャカ」という金属音的なバック音楽が繰り返し流れていて、横になって休んでいてもうるさい。とうとうお願いして止めてもらったが、たぶん従業員の好みなのだろうがイライラする音だった。こんな音が流れる山小屋は初めてであった。割り当てられた寝場所は定員6人であったが、この日はここに4人が横になった。隣の体格の良い人のイビキが酷く、急に無呼吸の状態にもなるし、ゴーゴーと唸るたびに床にも響くくらい。こんな時は千枚小屋でもそうであったが頭を皆と反対にして寝るとかなり被害を防げる。夕方の4時ごろになると深い沢の向こうに夕陽を受けて緑の聖岳が大きく見えだした。明日こそやっと期待していた展望の登山を楽しめそうだった。 5:00千枚小屋~5:30千枚岳~6:15丸山~6:40悪沢岳(荒川東岳)~7:40中岳~8:10前岳~8:50荒川小屋9:20~9:45大聖寺平~10:50小赤石岳~11:20赤石岳~12:50百閒平~13:40百閒洞山の家(泊) |
||||||||||||||
|
霧雨の千枚岳(2,880㍍) |
チシマギキョウとタカネビランジ |
タカネツメクサとタカネシオガマ |
||||||||||||
|
タカネマツムシソウ |
シコタンソウ |
悪沢岳(3,141㍍)荒川東岳 霧雨で展望全くなし |
||||||||||||
|
前岳斜面をトラバースするお花畑 ニホンジカの食害を防ぐフェンスが張られている |
フェンスを空けて中に入る 鍵を閉め忘れしないように |
|||||||||||||
|
クロユリ |
タカネシオガマ |
タカネツメクサ |
||||||||||||
|
ハクサンイチゲ |
お花畑 |
ミネウスユキソウ |
||||||||||||
|
ミネズオウ |
イワウメ |
|||||||||||||
|
イブキトラノオ |
ハクサンシャクナゲ |
ミヤマキンバイ |
||||||||||||
|
ヨツバシオガマ |
大聖寺平も霧の中、赤石岳も全く見えず |
|||||||||||||
|
雷鳥の親子(小赤石岳の登りで) |
|
赤石岳(3,120㍍)も素通り |
||||||||||||
|
一瞬、霧の中に赤石岳が見えた |
百閒平で青空が見えだした |
|||||||||||||
|
やっと山らしい景色になった 明日登る中盛丸山と大沢岳 山小屋までまだまだ下る |
百閒洞山の家に着いた 晴れ間を狙って濡れた衣類を乾かす |
寝場所は定員6人に4人が入る ここも寝具はシュラフ 隣の人のイビキが酷い、床にも響くので頭を反対にして寝た (-_-;) |
||||||||||||
|
平成29年8月4日(金) 変な夢を2~3回見ただろうか、ということは眠ったということである。隣のイビキの人は足が遅いからとまだ暗い3時には出て行った。窓から黒いシルエットの聖岳が見えている。晴れてはいるがたぶんこの晴れ間は朝だけだろう、早めに食事を済ませ登山開始。標高が上がるにつれて聖岳が緑に変わり、赤石岳も大きく見えだした。朝日に映えオレンジがかる雲の上に黒い富士山も見えだして嬉しくなってくる。大沢岳と中盛丸山の鞍部にザックを置いて大沢岳に向かう。朝露でズボンが濡れたがすぐに乾いてしまった。大沢岳(2,819㍍)山頂からは南アルプス北部の山々、特に大きな仙丈ケ岳、小河内岳の後ろに小さく甲斐駒ケ岳、そして特徴ある頂の塩見岳も見えている。間ノ岳の後ろは北岳だろうか。さらに昨日まで全く見えず今は遠くになった荒川三山が、深い谷を背景に赤石岳がどっしり座っている。2年前に歩いた中央アルプスの峰々も長々と横たわっている。御嶽山、恵那山、加賀の白山まで見える。振り返ると南には青い富士山、そして緑の聖岳に向かいうねるようにこれから縦走する山々が連なっている。ここは素晴らしい展望台だ。デジカメのパノラマ機能を使って名峰達を一気に収める。今度は失敗の無いように撮れたのをしっかり確認する。 鞍部に戻りザックを背負い再び登り始め、中盛丸山(2,807㍍)、小兎岳(2,738㍍)の山頂でも展望を楽しむ。通過タイムを記録しようとしたら鉛筆が無い。さっき花を撮ろうとデジカメを取り出したときに落としてきたようだ。ザックを小兎岳山頂に置いて5分ぐらい戻る。いつも前後する顔ぶれにすれ違うと、どうしたの‥‥と声を掛けられる。たかが小さな鉛筆なのだが、長年山行を一緒にしてきたので簡単に置き去りにはできなかった。結局探したが見つからずに諦めて小兎岳山頂に戻った。すると練馬の兄ちゃんがどうせ泊る小屋が同じだからとボールペンを貸してくれた‥‥ありがたい。小兎岳の山頂でいつもの4人がそろってしまい、昨日までと違った素晴らしい展望を喜び合った。実は大沢岳で遠望していたときは山々の名前がはっきりしていなかったのだ。話好きの岐阜の県庁退職の方が地図を広げながら丁寧に教えてくれた。すでに登った山々が多く、名前がわかると登った時の想い出も景色と重なって嬉しさも倍増してくる。恵那山、白山などまったく頭の中にはなかったのだ。小兎岳からは一旦鞍部まで下り、急登となって兎岳山頂まで続く緑の中の登山道もはっきり見え、登山意欲を駆り立てられた。昨日までは霧雨で全く展望が無い山行だったが、その残念な気持ちが吹っ飛んでしまった。思いがけず兎岳(2,818㍍)の山頂には千枚岳以来のタカネビランジが咲いていて、大きな赤石岳を背景に写真に収める。花の説明をしている人がいて、顔を見るとなんと百閒洞山の家で隣の寝場所だったイビキの人であった。再びいつものメンバーが山頂にそろってまたまた話し込んでしまった。時刻は8:00、やがて思った通り赤石岳に雲が架かり始めてきた。ここから急な下りを慎重に歩き、鞍部から今度は急登となった聖岳への登山道をハーハー言いながら登る。振り返ると兎岳から小兎岳、中盛丸山、大沢岳に連なる緑の縦走路が綺麗に見えている。歩いてきた道を振り返って眺めること、これこそ縦走の楽しみである。しかしやがてすべてが雲の中になってしまった。聖岳(3,013㍍)山頂も真っ白の世界。結局三つの百名山3,000㍍の頂はすべて展望の無い山となってしまった。残念ではあるが大沢岳から兎岳までの大展望の縦走ができたおかげで、聖岳山頂での悔しさはさほどではなかった。すぐに岩の尾根道を奥聖岳(2,982㍍)に向かう。奥聖岳は縦走路から外れているため山頂には全く人が来ない。向かい合う赤石岳の雲が部分的に取れるのを眺めながら、30分ほど大休憩にして昼食、そして家に無事の連絡をした。風もなく静かな山であった。 明るいが雲が架かって見通しの利かない尾根道を戻り、人影の聖岳山頂を横目に聖平への急な斜面を下り始める。ここから聖平小屋まで約700㍍を一気に下る。砂礫の長い下りが続き右足の指が摺れて痛くなってきた。カットバンを忘れてきたのを悔やんだがあとの祭り。霧の中にラクダのこぶのような尾根道が見え隠れして楽しくなる。小聖岳(2,662㍍)も過ぎ樹林が目立つようになって、やがて薊畑のお花畑。タカネマツムシソウやイブキジャコウソウ、タカネナデシコ、イブキトラノオ、マルバダケブキ、ハクサンフウロ、ミヤマキンバイなど色とりどり。とたんに歩きが遅くなって、防鹿柵の網の間からデジカメをさし込む。この鮮やかな場所と違って、聖平は裸地化が進み荒涼たる景色を見せていた。もともとニッコウキスゲを中心としたお花畑だったらしいが、今は草原に変わってしまった。この植生変化や裸地化の原因は人為的な踏みつけや不法採取、ニホンジカの採食による植生変化や踏圧、裸地表土の流出などらしい。現在、登山道整備や防鹿柵、ニッコウキスゲの植栽実験などで植物復元の対策が行われていた。やがて最後の宿泊地聖平小屋に着いた。12:40なんと今日最初の受付らしく寝場所は壁際のA1番であった、有難い (^_^)v。 受付が終わるとフルーツポンチのサービス。入口に置かれた鍋の中から紙コップに山盛りにして小屋の前のテントで食べる。靴の紐を解いて、天候に恵まれ撮影した今日の山々を再生しながら充実した時間を過ごした。次々に下山してきた登山者らは皆無事着いた喜びを顔に表していて、ついつい「こんにちは、お疲れ様でした」の声も大きくなった。いつもの3人も降りてきたが、結局寝場所はまたまた一緒になった。シュラフを敷いて横になっていると岐阜の県庁退職の方から聞かれた。「岐阜って聞いて何か思い出すことはある?」、私は「新幹線の岐阜羽島の駅、高山祭、白川郷、長良川の鵜飼い、関の刀、食べ物は‥‥ないですね」と話した。すると「そうでしょう、そんなもんで実は岐阜県は目立たない県なんですよ。食べ物はうまくないし、岐阜羽島の駅は政治駅だし‥‥」という。県庁に勤めていた方がそう言うならそうなんだろう。面白い方で、その後眠るまでいろいろな話をした。練馬の兄さんは「山小屋では眠れない」と話していたが、ゴーゴーと寝息を立てて寝ていた。朝になってそのことを話したら、「エー寝てたんですね、良かった」と笑顔だった。広島生口島の方だけは明日も縦走が続き、茶臼岳を経て光岳まで往復するという。「しまなみ海道は自転車の聖地で、自転車旅行者でいっぱい、ぜひ来てください」と話してくれた。自転車の旅が大好きな私は絶対この道も走るつもりでいる。この日が最後の山小屋、大満足の山旅を振り返りながらぐっすりと眠ることができた。 4:50百閒洞山の家~5:30百閒洞下降点~5:45大沢岳~6:00百閒洞下降点~6:10中盛丸山~7:00小兎岳~7:55兎岳~9:40聖岳(前聖岳)~10:00奥聖岳10:30~10:45聖岳~11:25小聖岳~12:00薊畑分岐~12:40聖平小屋(泊) |
||||||||||||||
|
百閒洞山の家から朝の聖岳を望む |
富士山が見えだした |
|||||||||||||
|
縦走路から外れて大沢岳(2,819㍍)へ登る |
御嶽山と中央アルプス(大沢岳から遠望) |
|||||||||||||
|
南アルプス北部の山々 仙丈ケ岳、小河内岳、甲斐駒ケ岳、塩見岳、間ノ岳 |
朝日と赤石岳、富士山、聖岳、兎岳、茶臼岳 |
|||||||||||||
|
この縦走で初めて荒川三山と赤石岳を撮れた |
兎岳から歩いてきた縦走路・綺麗な山々 大沢岳、中盛丸山、小兎岳、荒川三山、赤石岳 |
|||||||||||||
|
これから向かう緑の縦走路(聖岳、小兎岳、兎岳) |
タカネビランジと赤石岳(兎岳にて) |
|||||||||||||
|
小兎岳から兎岳、聖岳へと続く爽快な縦走路 |
兎岳(2,818㍍) |
|||||||||||||
|
前聖岳の登りから歩いてきた山々を振り返る (兎岳、小兎岳、中盛丸山、大沢岳) |
大きな赤石岳 これ以後は雲の中に |
|||||||||||||
|
聖岳(3,013㍍)山頂は雲の中 |
奥聖岳(2,982㍍)へ向かう |
チングルマ 3,000㍍の稜線でも咲いている |
||||||||||||
|
チシマギキョウ |
奥聖岳から聖岳を望む |
|||||||||||||
|
聖岳の斜面から小聖岳への道 |
薊畑のお花畑にて タカネマツムシソウ |
マルバダケブキ |
||||||||||||
|
イブキトラノオ |
タカネナデシコ |
裸地化・立ち枯れが目立つ聖平 伊勢湾台風(1959年)で倒木したらしい |
||||||||||||
|
聖平小屋 |
受付が終わるとフルーツポンチのサービスがある |
一番目の到着なので奥の壁際が寝場所、トイレは外で50㍍奥にある |
||||||||||||
|
平成29年8月5日(土) 今日の朝も晴天に恵まれたが、午後から大きく崩れそうな感じだった。朝食のときテレビの天気予報を見ながら、これから聖岳を目指す方々が接近する台風の影響を心配していた。こちらは当初の予定では聖岳登山口に下山してから車道を椹島まで約50分歩く予定だった。しかし聖岳登山口から無料で赤石温泉白樺荘まで向かう無料の送迎バスがあることを、4日前に畑薙臨時駐車場の登山案内所の方が教えてくれた。聖平小屋に泊った人へのサービスらしく、前日の受付の際に予約しておいた。出発の10時までに聖岳登山口に下山しなければならなかった。5時間もあれば降りられるだろうが、ゆっくり安全を考えて早めの下山となった。青空の見える樹林の中の道を下っていくと木々の間から聖岳が朝日を受けて輝いていた。山頂から奥聖岳までの尾根も見えていて、見送っているようで嬉しくなってくる。揺れる聖沢吊橋も楽しく、沢の音を背にどんどん下る。予定よりだいぶ早く8:00に登山口に着いた。井川観光協会送迎のマイクロバス(定員25名)はすでに到着していて運転手が木陰で昼寝していた。近くの水場で顔や手を洗い、テントの中で休んでいると「終わった~間に合った~」と、登山者が次々に下山してくる。再び小屋で一緒だった方々と疲れを労いあう。顔を出した運転手は「降りてきたら下山届を出して」と高圧的な言い方で、書き方が分からないで戸惑っている人には厳しい口調であった。気が荒いトラックの運転手が送迎バスの運転手をしている‥‥という感じで、ただで乗せてやるとでも思っているのか、かなり不愛想な感じの人であった。ここから4人乗車で10:00出発、途中茶臼岳登山口から10人ぐらいが乗り込んで、畑薙ダムの臨時駐車場でほとんどが降りる。結局白樺荘まで乗って来たのは3人だけであった。 白樺荘ではザックは建物の軒下に置いて着替えだけ持って温泉に向かう。入浴料は510円、露天風呂もあり5日間の山行の汗を流す。静岡に向かうバスの出発が14:35なので、広々とした休憩所で昼食代わりに非常食を食べながらのんびりする。座布団を枕にぼんやりとテレビを眺めて横になっていたら眠ったらしい。「お客さ~ん」と遠くで声がする。「バスに乗るんじゃないですか~」と言われてビックリして飛び上がる。「す、すみませ~ん」、時計を見ると14:20。慌てて荷物をまとめて廊下に飛び出すが頭の中はまだ夢を見ている状態でふらつく。まずトイレ、水の補給、また時計確認。外に飛び出し軒下のザックに風呂道具を押し込んで背負う、あと5分。バス停には5人ぐらいが待っていたが、焦っている姿を見せないようにしてザックを下してため息一つ「間に合った~」。一日に一本しかない「しずてつジャストライン」のバスを逃すと白樺荘に泊らなければならなかったのだ。予約制のバスで隣に若い人が座ったが、自由に空いている席にどうぞ‥‥の声で移っていった。再び井川駅で休憩。電車が止まっていたので写真に撮る。大井川鐡道井川線は南アルプスあぷとラインの愛称がついていて、日本で唯一のアプト式と呼ばれる歯車を線路にからめて登る電車なのだ。それほど急な路線で、大井川の流れに沿って山間を縫うようにゆっくりと走る。全線の1/3がトンネルと橋梁で占められ、さらに非常にカーブが多く走行中は車輪が軋む音が絶えないらしい。もともとダム工事の資材運搬のためにに使われたようだが、いまは利用者の大半が観光客のようだ。夏休みでもあり楽しそうな子供たちの声でいっぱいであった。ここでまたまたトウモロコシとトマトを買って、深い峡谷とそれを覆う緑の山々の景色を楽しみながら夕暮れの静岡駅前に降り立った。 4:50聖平小屋~7:05聖沢吊橋~8:00聖岳登山口10:00~(井川観光送迎バス・聖平小屋宿泊者無料)~11:00赤石温泉白樺荘(♨入浴・510円)14:35~(しずてつジャストライン・3,100円・要予約)~17:50静岡駅19:20~(新幹線)~20:47東京駅21:30~(高速バス)~6:45八戸駅7:00~(バス)~7:15自宅 |
||||||||||||||
|
聖平小屋からの下山道で樹間から聖岳が見送っている |
聖沢の吊橋、揺れます(^_^)v |
|||||||||||||
|
無事、縦走を終えて聖岳登山口に |
赤石温泉白樺荘で汗を流す 眠り込んでしまい、バスに乗り遅れるところだった (^_^;) |
井川駅のアプト式列車 駅前の露店でトウモロコシとトマトを買う |
||||||||||||
|
今回のコースは南アルプスらしい大きな山塊であり、花と稜線歩きを楽しめる。山岳雑誌の写真を見ると、山頂からは緑に覆われた雄大な山々を展望できるはずだった。それだけに千枚岳・悪沢岳から赤石岳の3,000㍍峰からの展望が無かったのが残念で仕方ない。しかし南アルプスの山深さは魅力的で、長い道のりではあるが来年は三伏峠から入り塩見岳に登り仙塩尾根を北に向かい、3年前も全く展望の無かった間ノ岳~北岳の3,000㍍の稜線を縦走し、鳳凰三山に登り青木鉱泉に下るという計画を立てている。 (H29.9.1) |
||||||||||||||