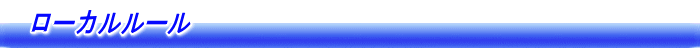
河川敷コースという地理的特殊条件等により、独特のローカルルールがあります。
以下主なものを紹介します。
- 隣接するホールの境界線は黄杭の上部に黒帯をもって表示し、打ったボールがその杭をオーバーしたときは、罰打1(それ以上の罰打は負荷しない)を加え、そのボールのある位置から真横のコース内のホールに近づかない1クラブ・レングス内の地点にドロップしなければならない。
- スルー・ザ・グリーン内に於けるネット、支柱、ベンチ、砂箱、吸ガラ入れ、マンホール(排水口)№2・4・8の水路に張ってあるロープ・杭は動かせない障害物とみなす。
№4ホールで、グリーンを超えてしまったボールがスルー・ザ・グリーン上にない場合は、池に入ったものとして、1打付加しドロップゾーンより打たなければならない。
- ウォーター・ハザードにボールが入った場合は、1打付加して打ち直すものとする。橋の上のボールは、安全上ウォーター・ハザードに入ったものとみなす。
- コース内を横切る高圧線に球が当たった場合、プレーヤーはそのストロークを無視してその球を放棄し、プレーした箇所にできる近い地点から、別の球をプレーしなければならない。
- №7、№8ホールでは、危険防止のためホールアウトするまでアイアン・クラブのみとする。
- グリーン上ではパター以外のクラブは使用できない。
- №9ホールのレギュラーティに於いて第一打がOBの場合は特設ティより第4打として打ち直さなければならない。ただし、公式戦は適用を除外する。

ゴルフ規則は4年に1度、オリンピックの年に改訂され、2016年は規則改訂年です。
2016年規則改訂は2016年1月1日より施行されました。以下はその主な変更点と解説です。
これは、「(財)日本ゴルフ協会資料」によります。
2016年ゴルフ規則の主な改訂点
改訂の概要
- クラブのアンカリングの禁止
クラブの一方を体に固定して安定点を作り、片方の手でクラブを振る、という打ち方を禁止する。この規定は、クラブの長さを制限しているわけではなく、球の打ち方についての規定です。また、この規定はパッティングだけでなく、すべてのストロークに対して適用される。
- 「アドレスしたあとで動いた球」が削除
アドレスしたかどうかは関係なく、プレーヤー以外のものによって球が動かされたことがほぼ確実であるという証拠があれば、1打の罰を課すという規定は適用しないことになった。
- スコアを誤記して提出した場合の罰の軽減
実際のスコアよりも少ないスコアを記入したスコアカードを提出した場合、プレーヤーは競技失格でしたが、場合によっては、2打の罰をそのホールのスコアに加えることに、罰を軽減する。
- 練習器具等を使用した場合の罰の軽減
これまでの規則では、正規のラウンド中に、プレーの援助となる人工の機器を使用した場合の罰は競技失格でした。この罰が軽減された。
- 距離計測機器の使用を認めるローカルルール
いままで使用が認められなかった2点間の距離を計測する機能以外の計測機能を持つ機器でも、2点間の距離計測以外の機能を使用しなければ、距離計測機器として使用することができるようになった。
- その他明確化のための改訂
改訂の詳細
- クラブのアンカリングの禁止(規則14-1b)
クラブの一方を体に固定して安定点を作り、片方の手でクラブを振る、という打ち方を禁止するために規則14-1bが追加されました。この規定は、クラブの長さを制限しているわけではありません。球の打ち方についての規定です。また、この規定はパッティングだけでなく、すべてのストロークに対して適用されます。
ゴルフは長いクラブを両手でコントロールする技術を競うゲームです。したがって、クラブを振るのではなく、クラブの一部を固定してそれを安定点として片手でクラブを打つという方法を規則は禁止したいのです。
安定点を作るためにクラブを意図的に直接体に接触させてはいけません。また、同様に安定点をつくるために、クラブを持っている片方の手を意図的に体に接触させてはいけません。安定点を作るために前腕を体に接触させることも禁止しています。
キーワードは「安定点を作るために意図的に」です。例えば、安定点を作る意図はなく、正しいストロークをする上で、たまたまクラブやクラブを握っている手、前腕が洋服に触れてしまっても違反とはなりません。
この規則に基づき規則で禁止される打ち方についての詳細なガイドライン(写真つき)はJGAホームページに掲載されていますのでご参照ください。
- 規則18-2b「アドレスしたあとで動いた球」が削除(規則18-2)
これまでの規則では、アドレスしたあとで球が動いた場合、プレーヤーがその球を動かしたものとみなされ、プレーヤーは1打の罰を受け、その球をリプレースしなければなりません。この自動的にプレーヤーに罰を課すことになる「みなし規定」は固くて速いグリーンをプレーするプレーヤー達を悩ませてきました。プレーヤーに原因がなくても、アドレスしたあとで球が動いた場合、罰を受けることになるからです。そこで2012年規則では例外規定を設けて、プレーヤー以外のものによって球が動かされたことがほぼ確実であるという証拠があれば、1打の罰を課すという規定は適用しないことになりました。この時点で、事実上、規則18-2bの持つ「みなし規定」の意味は無くなりました。
2016年規則では規則18-2bを削除し、アドレスしたかどうかは関係なく、プレーヤーの止まっているインプレーの球が動かされた場合、プレーヤーサイドに原因があればプレーヤーは1打の罰を受けてリプレース、プレーヤーサイドに原因がなければ罰なしに新しい位置から(ただし他の規定が適用となる場合は除きます)プレーしなければなりません。
今回の改訂により、規則18-2は2000年規則まで規定されていた規則18-2c「球から1クラブレングス以内にあるルースインペディメントを取り除いたあとに球が動いた場合はプレーヤーが動かしたものとみなされる」というみなし規定の削除に続き、規則18-2bが今回削除されることで、とてもシンプルになりました。
- スコアを誤記して提出した場合の罰の軽減(規則6-6d例外)
スコアカードを提出する場合、プレーヤーは各ホールのスコアが正確であることについて責任を持ちます。そして実際のスコアよりも少ないスコアを記入したスコアカードを提出した場合、プレーヤーは競技失格となります。2016年規則ではこの違反に対して新しい例外を規定し、罰を軽減しています。もし、プレーヤーが罰を受けていたことを知らなかったために、その罰を加えずにスコアカードを提出してしまったことが競技終了前に発覚した場合には、罰は競技失格ではなく、その受けた罰と、この規則に規程されている2打の罰をそのホールのスコアに加えることになります。
例えば、プレーヤーが5番ホールで、バンカー内の球の後ろにあった枯葉を取り除いてしまいました。プレーヤーはその行為が規則13-4の違反とは知らず、本来課さなければならない2打の罰を加えずにスコアカードを提出しました。このことが競技終了前に発覚した場合、委員会は規則6-6d例外に基づき、スコアの修正をすることになります。このプレーヤーの5番ホールのスコアには、本来課さなければならない規則13-4違反の2打の罰と、規則6-6d例外の2打の罰の合計4打の罰が課されます。
この例外規定は罰を受けていたことをプレーヤーが知らなかった場合に適用されます。罰を受けていたことを知っていながら、その罰を加えずにスコアカードを提出した場合は、これまでどおり、競技失格となります。
「罰を知らなかった」という解釈には、本来2打の罰であったところを、規則を知らずに1打の罰を課してしまったケースも含まれます。この規則6-6d例外の規定はあくまでもスコアカードを提出した後で、競技が終了する前に、罰を課していなかったことが発覚した場合に適用されます。一方で、競技がすでに終了した後に、罰を知らなかったためにその罰を追加せずにスコアカードを提出していたことが発覚した場合、そのプレーヤーのスコアは修正できません。(規則34-1b例外参照)
- 練習器具等を使用した場合の罰の軽減(規則14-3罰則)
これまでの規則では、正規のラウンド中に、プレーの援助となる人工の機器を使用した場合の罰は競技失格でした。例えば、正規のラウンド中に練習器具や、違反手袋を使用してスイングをチェックした場合です。2016年規則では、この罰が軽減され、最初の違反についてはマッチプレーではそのホールの負け、ストロークプレーでは2打の罰となります。そして、それ以降にまた同じ違反があった場合は、競技失格となります。
例えば、ティーショットで違反となる手袋を使用し、同じ手袋をしたまま第2打もプレーした場合、このプレーヤーは競技失格となります。
- 距離計測機器の使用を認めるローカルルール
正規のラウンド中、距離計測機器を使用することは原則禁止されていて、ローカルルールでその使用を認めることができるという規定は2016年規則でも同じです。
ローカルルールでその使用が認められる場合、これまでの規則では2点間の距離を計測する機能以外の計測機能(例えば、風向き、風速、標高差など)を持つ機器は、例えそれらの機能を使用しなかったとしてもその機能を距離計測のために使用することはできません。例えば、距離以外の状況を計測できるナビを搭載したカートは、ローカルルールのもとであっても使用することはできませんでした。
2016年規則では、規則では認められない計測装置やアプリを搭載されている機器(スマートホォンなど)であっても、2点間の距離計測以外の機能を使用しなければ、距離計測機器として使用することができるようになりました。
- その他明確化のための改訂
2016年規則では内容はこれまでと変わらないものの、読みやすくするための改訂が行われています。例えば、処置について疑問がある場合に2つの球をプレーすることができる規則3-3の規定は競技者のための処置と、委員会側の処置について区別するように再構成されました。また、ウォーターハザード内からプレーした球がまたそのウォーターハザード内に入ってしまった場合の処置について規定する規則26-2では罰が合計でいくつになるのかを明確にするために改訂されました。付属規則1では(A)をローカルルール、(B)を競技の条件とし(C)が削除されました。
![]()